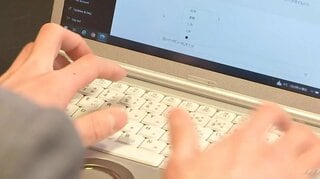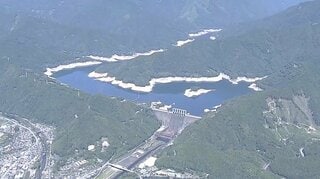家庭の経済状況によらない「教育の機会均等」を
とはいえ、すべての「隠れ教育費」を国が負担し、「完全な教育無償化」とするには安定財源が足りない可能性がある。そこで、「隠れ教育費」の内容に優先度を付け、段階的に無償化していくのはどうだろうか。
優先度が高い「隠れ教育費」として挙げられるのが、「学校給食費」である。前述の学校教育費の内訳をよくみると、給食費が入っていないことがわかる。小・中学校においては、学校教育費に加えて給食費が加算されて家庭が支払う必要があり、これもまた「隠れ教育費」の一部になっている。特に、複数の子どもがいる家庭や経済的に困難な家庭にとって、給食費は相当の負担となることがある。給食費を無償化することは家庭の経済的負担を軽減するメリットがあるため、無償化を行うことで、これらの負担が軽減され、子どもたちが安心して学校生活を送ることができるようになる。
給食費を無償化するためには、自治体がその費用を負担する必要があるが、財政状況が厳しい自治体では、無償化の実施が難しいだろう。また、無償化を実施している自治体とそうでない自治体の間で不公平感が生じるという指摘もある。さらに、給食の質の維持も重要な課題だ。物価が高騰するなかで、栄養バランスの取れた給食を提供し続ける必要がある。現在、全国の自治体の約3割で給食費の無償化が実施されているが、全国的に拡充させるためには国の施策に位置付ける必要がある。こうした背景もあり、2024年12月には立憲民主党・日本維新の会・国民民主党の野党3党が合同で給食費無償化の法案を国会に提出している。
一方、文部科学省は、給食費の無償化について慎重な姿勢を取っている。全国の学校で給食の提供を受けている児童・生徒は約880万人いる一方で、アレルギーなどの個別の事情で、弁当を持参したり、不登校の場合など、学校給食を食べていない子どもが全国に約60万人いるため、仮に一律に無償化しても、こうした人たちに恩恵が及ばないと指摘している。また、生活が困窮した世帯に対しては、基本的にすでに無償化されているため、格差是正の観点も乏しいとしている。さらに、公立学校に限って実施した場合でも、食材費として約4,800億円の安定財源の確保が新たに必要になるとして、全国で学校給食費の無償化を行うべきかどうか、子育て支援や少子化対策の観点からも、丁寧に議論を進めていくとしている。
もちろん、給食費に限らず、教育無償化の議論においては、財源の確保や教育の質の維持、負担の支え合いなどの課題に取り組むことが求められる。そのうえで、今後の議論では、これまで見過ごされてきた「隠れ教育費」の見直しまで視野に入れ、すべての子どもが経済的な状況に左右されず、平等に教育を受けられる環境の整備を図っていく必要があるのではないだろうか。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主任研究員 西野 偉彦)