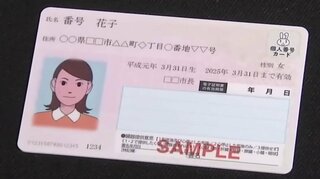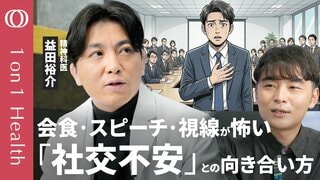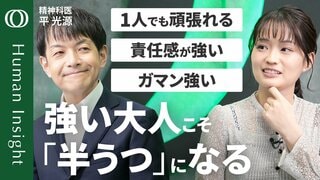「教育無償化」とは何か
2024年12月、自由民主党・公明党・日本維新の会の与野党3党による教育無償化に関する実務者協議が開始された。この協議では、まず「高校授業料の無償化」を先行して議論することとなり、大学などの高等教育の無償化についても順次取り上げられる。今後、早期に一定の結論を得るべく協議が加速されるものとみられる。
教育無償化は、現代社会において重要な政策の1つである。そもそも、教育は個人の成長と社会の発展に不可欠であり、そのためにはすべての人に平等な教育機会を提供することが必要になる。その点で、教育無償化の最大の意義は、教育の機会均等を実現することである。無償で教育を受けられるようにすることで、経済的な理由で教育を受けられない子どもたちが減少し、すべての子どもが質の高い教育を受けられるようになる。これにより、個人の能力を最大限に引き出し、社会全体の教育水準を向上させることが期待される。
現在、日本ではいくつかの教育段階において教育無償化が実施されている。まず、小・中学校(義務教育)の無償化は日本国憲法の第26条第2項に明記されている。この条文は、すべての国民が法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うこと、そして義務教育は無償であることを規定したものだ。この義務教育の無償化では「授業料を徴収しない」ことが定められており、教科書も無償で提供されることとなっている。
一方、高等学校の無償化については、日本国憲法に規定されていない。その背景として、憲法制定の頃の高校進学率は40%程度に過ぎず、高校の教育はすべての国民が受けるわけではなかったことも、無償化の対象から外された理由の1つとされている。その後、高度経済成長期などを経て、日本における高校進学率は上昇の一途を辿り、2020年度には98.8%に達するなど、現在ではほぼすべての国民が高校に進学しているといえる。こうしたなかで、国は高校の無償化に準ずる政策として、2010年から「高等学校等就学支援金制度」を導入したが、その対象になるには通学する高校の種類や世帯収入に一定の条件が課されている。
地方自治体をみると、2024年度から東京都は所得制限を撤廃する高校の無償化を導入した。もともと東京都では、都立高校は国の支援で無償化され、私立高校については、東京都が国の支援に上乗せして都内にある高校の授業料の平均額を上限に助成するなどしていた。今回その上限が撤廃され、都立・私立にかかわらず高校の無償化が実現された。無償化の条件は都内に保護者が在住していることであり、都外の私立高校への通学者も対象となったことで、近隣自治体から東京都に人口が流入する可能性も指摘されている。こうした状況を受け、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の各知事と、5つの政令指定都市の各市長から構成される会議では、子どもに関する施策に居住地域によって差が生じないようにするため、国の責任と財源で無償化することを求めた。また、東京都以外では、大阪府でも段階的に私立高校の無償化が始まっており、2026年度より府立・私立ともに高校の無償化が実現する見込みである。