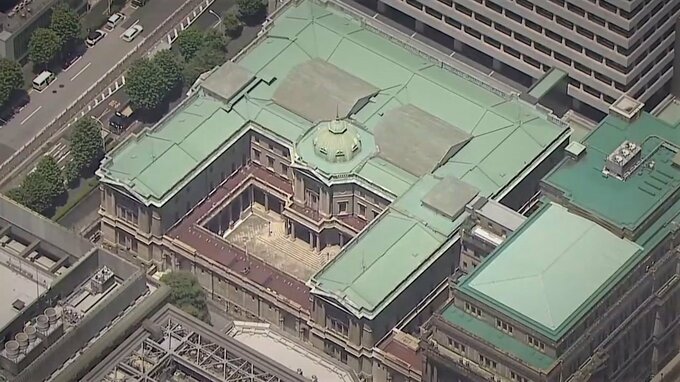記事のポイント
・FRBと日銀はいずれもトランプ氏の政策に対して「慎重化」した
・なぜ「多角的レビュー」の重要性は低下したのか
・これまでの異次元緩和からの脱却のペースは想定以上に早かった
・利上げのタイミングが遅れ、ターミナルレートは低水準になる可能性
・「ノルム」の分析がなく日銀への「批判」が注目された「多角的レビュー」
FRBと日銀はいずれもトランプ氏の政策に対して「慎重化」した
12月17-18日の米FOMCはタカ派、18-19日の日銀決定会合はハト派という対照的な結果となった。いずれも政策決定そのものは事前の予想から大きく乖離したものではなかったが、記者会見でタカ派・ハト派が鮮明化した。いずれの中央銀行もトランプ次期米大統領の政策リスクに対して警戒感を強めていることが、今回のスタンスの違いになったと考えられる。FRBにとってはインフレ再燃が金融政策の運営上で最大のリスクであり、「予防的タカ派」の必要があったのだと、筆者はみている。日銀にとっての最大のリスクは、円安とそれに対して不必要な利上げが避けられなくなることだろう。今回は利上げの「弾」を温存した可能性がある。
むろん、植田総裁は「金融緩和度合いを私どもの見通しに応じて調整していかなかった場合には、場合によってはですけれども、どこかでインフレ率が急に加速するとかいうことが発生して、急速な金利の引き上げを迫られるという可能性もゼロではないわけです」(24年11月18日、日銀会見録)と述べていたことから、早期に利上げの「弾」を使っていくことが最適だと考えれば、利上げを実施するだろう。とはいえ、おそらく日銀はそれほど利上げの「弾」が残っていないと考え、慎重化している可能性が高い。
そもそも日本経済が力強く成長し、完全にデフレ脱却に成功したと言える状況であれば、今回の12月決定会合で利上げの「弾」を使うことを躊躇していなかっただろう。利上げに対する慎重さや海外経済を気にする姿勢は、日本経済への自信のなさの裏返しである。
なぜ「多角的レビュー」の重要性は低下したのか
今回、日銀は「多角的レビュー」の結果を公表した。ポイントについては後述するが、そもそも「多角的レビュー」とは何のために実施されたのかという点を今一度考える必要がある。これは、植田総裁が政策が複雑化して泥沼化していた異次元緩和に区切りをつけ、普通の金融政策に回帰するための1つのきっかけにするために始まったものだと、筆者は解釈している。むろん、日銀が組織として過去を全否定することは考えにくいため、きっかけというよりも形式的な儀式のようなものに近いのかもしれないが、組織として考えをリセットするには有効な手段だったと考えられる。
しかし、異次元緩和からの脱却は「多角的レビュー」よりも先に訪れた。円安が進む中で金融緩和からの脱却が避けられなくなり、24年3月にYCCとマイナス金利は解除された。おそらく想定よりも早く異次元緩和から脱却したことにより、今回公表された
「多角的レビュー」は異次元緩和の効果を後から正当化するような位置づけの資料になってしまった。仮に、依然として異次元緩和が続いていたとすると、今回の「多角的レビュー」はもっと注目されていたのだろう。