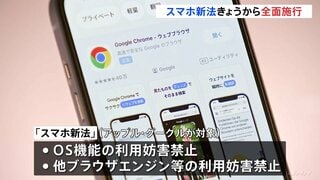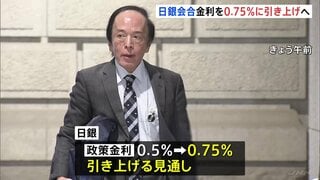2024年から、新NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」がスタートした。積立投資だけでなく、一括投資もできるなど使い勝手が良くなった新NISAで、私たちは積立投資と一括投資のどちらで老後資金等の資産形成をしていったら良いのだろう。
同じ元本で、積立投資と一括投資を行った場合、いくらになるのか?
「国内債券型」、「外国債券型」、「日本株式型」、「全世界株式型」、「先進国株式型」、「米国株式型(S&P500)」、「米国株式型(ナスダック100)」の7つ代表的な市場インデックスに連動する商品にそれぞれ投資をした最終時価残高を確認する。また、積立投資と一括投資の特徴を明らかにするため、投資期間を10年と20年に分けて合計4パターンで検証する。
パターン(1) 投資期間10年、毎月2万円積立投資(毎月2万円×10年×12か月=240万円投資)
パターン(2) 投資期間20年、毎月1万円積立投資(毎月1万円×20年×12か月=240万円投資)
パターン(3) 投資期間10年、投資開始時一括投資(投資開始時に240万円投資)
パターン(4) 投資期間20年、投資開始時一括投資(投資開始時に240万円投資)
これら4パターンで、1989年10月末から1か月ずつ投資開始期間をずらしてシミュレーションを行い、その結果を確認する。時価の下の( )内は元本に対する倍率である。

投資期間は長い方が良い
積立投資でも一括投資でも、投資期間が長ければ長いほど最終時価残高が大きくなる。投資期間が10年でも20年でも、各投資対象全てで最終時価残高の平均値は投資元本を上回っているが、投資期間10年に比べて、投資期間20年の最終時価残高は元本に対する倍率が大きい。
例えば、米国株式型(S&P500)への一括投資だと、同じ投資元本240万円に対して、10年間での最終時価残高の平均値が670万円で元本の2.8倍にとどまっているが、20年間での最終時価残高の平均値は1,130万円で元本の4.7倍にもなっている。この結果から判断すると、投資期間は長い方が良い投資結果をもたらす可能性が高いと言える。
短期的な価格変動リスクが高くても、高いリターンが期待できる投資対象を選んだ方が良い
市場インデックスはある一定のルールに基づいて選択された銘柄群に投資するもので、銘柄分散されているが、株式インデックスはインカムを定期的にもらう債券インデックスよりも短期的な価格変動が大きい傾向にある。投資期間が10年と20年の場合、投資方法は積立投資でも一括投資でも、最終時価残高の平均値と最大値は、大きい方から概ね米国株式型(ナスダック100、S&P500)、先進国株式型、全世界株式型、外国債券型、国内債券型の順となっている。10年以上の長期投資なら、投資をいつ始めても、この順序はほとんど変わらないということだ。尚、日本株式型は例外なので、のちほど説明する。
具体的に平均値を見てみると、20年での一括投資(投資元本240万円)だと、米国株式型(ナスダック100)が1,392万円、米国株式型(S&P500)が1,130万円、先進国株式型が1,030万円、全世界株式型が876万円、外国債券型が649万円、日本株式型が433万円、国内債券型が393万円となっている。
10年とか20年以上の長期投資では、短期的な価格変動リスクが高くても、高いリターンが期待できる投資対象へ投資したほうが実際に高い最終時価残高を獲得する可能性が高いと言える。
尚、日本株式型(日経平均株価)は、1990年以降の「日本バブル崩壊」の長期低迷の影響を受け、試算した投資期間10年の最終時価残高の平均値は債券型とほぼ同じである。一方で、投資期間20年の場合は、2012年末からのアベノミクスによる量的・質的金融緩和政策などによって、価格上昇の恩恵を受けたケースが多くあり、外国債券型よりも最終時価残高の最大値が大きくなっている。日本株式の 値動きはアベノミクス以降に大きく変わったと見ることができる。