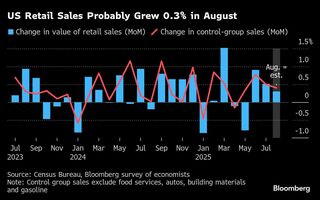(ブルームバーグ):全国の物価の先行指標となる11月の東京都区部の消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)は、エネルギー価格の上昇幅拡大を主因に3カ月ぶりに伸びが拡大した。事前予想を上回り、市場で日本銀行による早期の利上げ観測が一段と高まる可能性がある。
総務省の29日の発表によると、コアCPIは前年同月比2.2%上昇した。市場予想は2.0%上昇だった。日銀が目標とする2%を上回るのは2カ月ぶり。政府による電気・ガス代の補助金縮小に伴いエネルギーは7.4%上昇と前月から伸びが加速した。生鮮食品を除く食料も4.0%上昇と8カ月ぶりの高い伸び。コメ類のほか、チョコレートや調理パンなどがプラス幅の拡大に寄与した。
生鮮食品とエネルギーを除くコアコアCPIは1.9%上昇と、前月の1.8%上昇から伸びが拡大した。市場予想と同じだった。
日銀は経済・物価の改善に応じて緩和度合いを調整する姿勢を維持する一方、追加利上げの時期について明確なメッセージは出していない。植田和男総裁は21日、現時点で同会合の「結果を予測するのは不可能だ」と述べ、それまでに利用可能なデータや情報を基に判断する考えを示していた。今回の結果は2%の物価目標実現の確度の高まりを示唆しており、利上げ判断を後押しする材料となり得る。
SMBC日興証券の宮前耕也シニアエコノミストは、今回の統計で食料の伸びが確認されたが、コメ以外に広がりが見られたことが特徴だと説明。コアコアは7月を底に上がってきており、経済・物価は「日銀の言うオントラック(想定通り)という見方でいいだろう。正常化を妨げるものではない」との見方を示した。

CPI発表後、東京外国為替市場の円相場は対ドルで上昇幅を拡大。一時1ドル=150円01銭を付けた。発表前は151円30銭付近だった。
賃金動向を反映しやすいサービス価格は0.9%上昇と6月以来の高い伸びとなった。日銀が政策判断で重視している賃金と物価の好循環に関して植田総裁は、特にコストに占める人件費の比率が高いサービスの価格がしっかり上がっていくかに注目している。
ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎経済調査部長は、「企業がコストを価格に転嫁している。現時点で好循環と呼べるかは分からないが、賃上げから物価を引き上げる動きはある」と語った。その上で、「物価が加速し過ぎて日銀がビハインド・ザ・カーブ(後手に回る)になることを示唆するものはなにもない。物価は鈍化傾向だと思うが、一方で心地よいレベルで動いているともいえる」との見方を示した。
総務省の説明
- 政府の「酷暑乗り切り緊急支援」がおよそ半減したことがコアCPIの上昇幅拡大に寄与。支援による押し下げ効果は0.32ポイント。支援がなかった場合は2.5%上昇
- 宿泊料はインバウンド(外国人訪日客)増加による宿泊需要増を反映し上昇幅拡大に寄与した
- 一般サービスの伸び拡大に寄与した項目は家事関連サービスと、外国パック旅行費と宿泊料を含む通信・教養娯楽関連サービス
(詳細とエコノミストコメントを追加して更新しました)
--取材協力:氏兼敬子、藤岡徹.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2024 Bloomberg L.P.