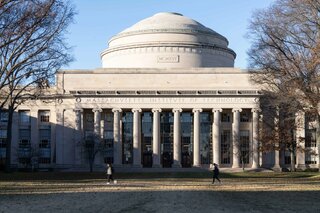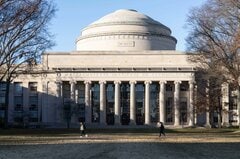保険料負担の行方
厚生労働省は、社会保険料の壁対策として、年収106~125万円程度までの範囲で、企業側に負担増を求める案があるようだ。これは、パート労働者の手取り収入を減らさないために、106~125万円程度で生じる社会保険料負担を、企業側に負担させるという手法だ。年収125万円の場合、パート本人の社会保険料は17.7万円(=125×14.15%)の負担増で、手取りは125-17.7=107.3万円になる。パート労働者が年収を106万円から125万円程度まで増やしても、そのときに増加する社会保険料を企業側が負担すれば、段差が生じにくいという理屈になる。ただし、企業の社会保険料負担は、労使折半ではなく100%負担になる。案の中では、106万円から金額が125万円程度に増えると、企業の負担率は徐々に100%よりも引き下げていくことを検討しているようだ。いずれにしろ、企業にとっては106~125万円程度のパート労働者を雇うと、負担増になるので、賃上げをすることも嫌がることになるだろう。106万円以上のパート労働者を増やしにくい点について、中小企業の「雇い控え」が起こりはしないだろうか。
厚生労働省はすでに「年収の壁・支援強化パッケージ」を設けて、手当等支給メニュー・労働時間延長メニューを提供している。手当等支給メニューでは、1人当たり助成額を賃金の15%以上を助成した場合は、1年目と2年目は20万円、3年目は18%以上を前提に10万円という条件で支給する対応になっている。厚生年金保険料+健康保険料が14.15%だとすると、それをカバーできる15%以上の賃上げを行って、106万円で▲15万円の負担増が生じても、1・2年目は20万円の助成金をもらって穴埋めすればよいという考え方なのだろう。労使折半の社会保険料を106〜125万円程度のパート労働者について、企業側に多く負担させる理由は、この支援パッケージをなるべく使わせたいという思惑もあろう。この対応がうまくワークするには、中小企業に対してこの制度をよく周知する必要がある。
また、労働時間を週20時間未満に抑えるパート労働者が増える懸念についても、支援パッケージの労働時間延長メニューで、1人当たり助成額を30万円と設定している。企業にインセンティブを与えて、防止しようと考えている。こうした困難を回避しようとすれば、週30時間以上に境目を見直す方がずっと摩擦が少ないと感じられる。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生)