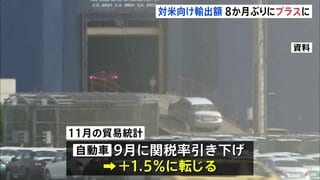「年収の壁」問題は、手取り収入に大きな段差ができることに問題がある。本人の手取り収入は103万円のところに段差はほとんどなく、扶養している親・配偶者のところで大きい。段差が大きいのは、むしろ「106万円の壁」の方だ。今後、社会保険料の負担は、労使折半のルールを変えるようだ。年収106〜125万円程度の範囲では、企業側の負担を引き上げる案があるものの、企業側は抵抗するだろう。政府は支援パッケージを用意するが、それは十分には活用されにくいという懸念がある。
「年収の壁」の誤解
政治的に「年収の壁」問題が焦点になっている。多くの人と議論していて気づくことがある。簡単に「壁」と称しているが、壁ではないものまで壁だと言われている。ここでいう壁とは、その境目を超えると途端に手取り収入が極端に減ってしまうケースだ。103万円は本当に壁と言えるのか。
まずは、数値例をみてみよう。年収が104万円になったときの税金はいくらになるだろうか。控除額は103万円だから、課税されるのは1万円(=104万円-103万円)だ。所得税5%が500円(=10,000万円×5%)、住民税が6,000円(所得割10,000円×10%+均等割5,000円)で合計6,500円になる。手取りは1,033,500円になる。年収103万円に比べて年収104万円の方が手取り収入は3,500円ほど増えている。ここでは手取り収入の大きな段差は生じていない。
厳密に言えば、住民税に均等割5,000円がかかるので、完全に段差が生じない訳ではない。年収103.5万円のときは1,029,250円と目減りする。しかし、この逆転は年収1,035,883円以上になれば解消される。だから、壁は事実上ほとんどないと言える。
問題になるのは、本人の課税ではなく、親や配偶者の扶養から外れることだ。親には扶養控除38万円や特定扶養親族の控除(19歳以上23歳未満)63万円などがある。子供の年収が増えると、この所得控除がなくなるから問題なのだ。親は、子供の年収が103万円を超えないように言い含める。ここで「働き控え」が起こる。所得控除を103万円から一気に178万円に引き上げる対応は、少しやり過ぎ感があるので、ひとまずは120万円程度に引き上げるのが妥当だろう。
一方、世帯主の配偶者の場合は、扶養控除ではなく、配偶者控除がある。103万円の年収を超えると、配偶者特別控除を使えば年収150万円まで課税されない。150~201万円までの年収の人は、徐々に配偶者控除の金額が圧縮されていく。手取り収入に段差を作らないためだ。
いずれにしても、年収が150万円を超過しても、手取り収入が逆転するようなことは起こらない。201万円でもそうだ。だから、配偶者控除にも「壁」=手取り収入の段差は発生しない。「150万円の壁」、「201万円の壁」という表記はやや疑問だ。