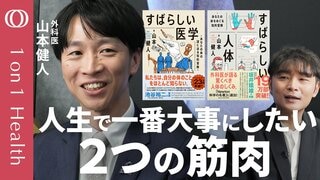この2つの裁判例が示す課題と解決に向けての考察~地域と金融機関の見守り連携~
この2つの例は、公序良俗違反や消費者契約法抵触を取り上げて、遺言や契約を無効としたものであるが、一方遺言能力や行為能力そのものを否定したものではない。ここに大きな課題が潜んでいると考える。
今後の長寿時代においては、本例のように高齢者の信頼や高齢者の認知特性(注意力や集中力の低下など)や行動特性(誤誘導に脆弱など)を利用した不正について、どのように防止策を作り上げなければならないかが問われていることになる。
つまり、身元保証代行など高齢者向けサービスを提供する事業者や士業者は、高齢者に寄り添い相談を受けることが多いことから、高い信頼を得ることが容易に想定される。そのため、一線を越えないための透明性を確保する仕組みが必要になる。例えば、組織において組織内の不正に対してのけん制機能として、担当先への第三者の関与(例えば上司など)であり、また不正に対しての社内通報制度の強化などがあげられる。また、地域全体(家族・事業者・行政などの連携)においてそれぞれがけん制可能な見守りの役割を果たすことも重要である。最近では地域包括支援センターを中心に高齢者サポートが行われており、金融機関との連携も進み始めている。
もっとも現在においても、金融機関は不正払い出しの防止において重要な役割を担っているが、今後の長寿時代は、地域全体でのサポートが重視されており、そのような地域サポート制度設計においては、金融機関によるお金の見守りについて果たす役割は特に大きいと考える。〈事例2〉においても地域金融機関が支払いを拒んだことで問題が発覚したと言っても過言ではないかもしれない。銀行等の金融機関は、法令に基づく規制・監督や、組織内の牽制も比較的整っていると思われることから、今後地域における信頼できる高齢者等サポート体制の一翼として、今まで以上に踏み込んだお金の管理機能を自治体や事業者に提供し、不正防止につなげる
役割を担っていくことも期待されている。
情報提供、記事執筆:MUFG相続研究所(三菱UFJ信託銀行) 首席研究員 小谷亨一