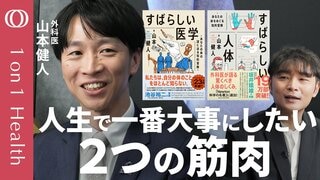近年、高齢者の判断力低下や高齢者心理を悪用したとして、いくつかの公序良俗違反の判決が出ている。今後、長寿時代・おひとりさま時代においてこの問題は極めて重要であると考えられる。そこで今回2つの例を紹介しながら、今後のあり方の一例を考察する。
〈事例1〉大阪高等裁判所判決/平成25年(ネ)第1687号
概略)遺言者は、遺言作成当時87歳という高齢であり、ひどい物忘れや短期記憶力の低下等アルツハイマー病の初期症状が出ていた。その後、89歳で秘密証書遺言を作成、作成当時症状がさらに進行・悪化していた状況において、作成した遺言内容はそれまで多くの相談をし、信頼していた弁護士に財産を遺贈するというものになっていた。
判決を要約すると「認知症の患者は目の前の人の言うことが全てという考えに陥りやすく、他者に迎合しやすい傾向が一般的に認められる。そのような状況下、弁護士資格を有し、種々の相談に乗ることが可能な人物の影響は非常に大きく、相談に乗る中で遺言者の判断能力や思考力、体力の衰えや同人の孤独感などを利用して、遺言者の真意の確認よりも合理性を欠く自己の利益を図る目的で遺言作成に不適切に関与し、5億円以上にわたる遺贈を受けようとした。これは、依頼人の信頼と無思慮に乗じ、弁護士として依頼内容実現のための最善の措置をとるべき誠実義務(弁護士法1条)や高い品性の保持(弁護士法2条)に違反し、著しく社会的相当性を欠いた」とし、遺言者の遺言能力は認めたものの、その内容に関し自分に有利になるようなバイアスを与えたとして公序良俗違反を理由に本自筆証書遺言及び秘密証書
遺言を無効としている。
〈事例2〉名古屋地方裁判所岡崎支部判決/平成30年(ワ)第624号、令和2年(ワ)第282号
概略)身寄りのいない高齢者の身元保証代行を請け負う特定非営利活動(NPO)法人は、市養護老人ホームへの身寄りのない入所者に対して身元保証契約と私署の死因贈与契約を一体として締結した。
その後入所者の死亡に伴い、当該NPO法人が死因贈与契約に基づき払い出しを行なおうとした際に、預金先金融機関が、契約書に不備があることや過去に他の入所者遺族とも争いとなっていた事実をもって支払いを拒んだことから訴訟となった。
地裁判決は、本契約に関し、市養護老人ホーム及び当該NPO法人は、本件において身元保証契約を締結する必要がないことを知りながら、入所者が保証人をつけなければ市養護老人ホームを退所しなければならないかもしれないという不安に乗じて、本件身元保証契約及び死因贈与契約を締結し、その行為は判断能力の衰えた高齢者の保護を図る消費者契約法4条3項5号(現在は同4条3項7号)に抵触すること、かつ本件死因贈与契約は公正証書によるものではなく、入所者の意思確認を確実にしているとはいえない上、その内容に関する説明もほとんど行っておらず契約締結課程に問題があったとした。
また身元保証契約内容に関しても債務履行可能性のない内容が含まれていたこと、同契約にある登録料や管理費との名目の内容が不明確であること、さらに本件における費用負担は身元保証契約時の預り金で足りており、そもそも死因贈与契約を行う必要がないため、この契約は明らかに対価性を欠き暴利であるといわざる得ないこと、本件死因贈与契約の執行者は、受贈者が担っており死後事務を適切に行ったことを確認することができなくなっていることなどをあげ、本件死因贈与契約は問題があるとして本件死因贈与契約は平成29年法律第44号による改正前の民法90条の規定する公序良俗に違反し、無効であると認定するのが相当であるとしたもの。