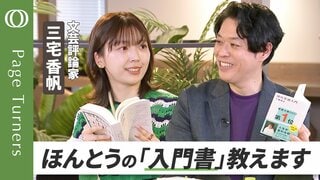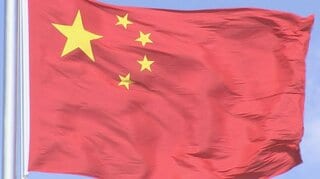値上げ幅が小さいのはエビ・鶏肉・きのこ類
次に、同様のことを、生鮮食品である魚・肉・野菜でも行ってみた。魚介類は、コロナ前に比べて、平均して25.3%も値上がりしていた。これは、肉類の17.7%、野菜・海藻の21.3%、果実の21.1%よりも値上がり幅がより大きい(前掲図表2)。魚介類は、漁船の燃料費や養殖魚のエサ代などの高騰の影響を受けやすいから値上がりしているのだろう。そうした中で相対的に値上がり幅が小さいのは、エビの8.3%であった。ほかは軒並み上がっていて、割安の魚介類は見当たらなかった。
肉類では、どうだろうか。こちらも国産牛肉の9.7%が相対的に低い。しかし、国産牛肉はもともとの値段が高いので、輸入牛肉に比べて国産牛肉が割安だとは言いにくい。強いて言えば、鶏肉がコロナ前に比べて10.9%と牛肉・豚肉よりも伸びが低い。肉類で値上がりを避けるには、鶏肉を選択する方法があると言えそうだ。
野菜・海藻では、アスパラガスの4.8%が上昇幅が小さい。生鮮野菜は、価格の季節変動が大きいので、8月時点の価格が低くなっていても、それはたまたまの変化である可能性が高い。全体の傾向では、野菜の中で総じてきのこ類にお得感がある。しめじは▲1.0%、生しいたけは7.5%、えのきたけは7.8%、干しいたけは6.0%となっている。秋の味覚のきのこ類が割安なのは朗報である。
飲料にはお買い得感
ほかの種類をみてみると、油脂・調味料は18.2%、お菓子は26.4%、調理食品は18.0%、飲料は13.5%、一般外食は14.0%となっている(図表3)。この中で、飲料にはお買い得の品目が多かった。例えば、茶飲料は▲6.5%、ビールは▲5.7%、乳酸菌飲料は0%である。この乳酸菌飲料は、ずっと価格変動がなかった点で驚きである。
一般外食では、パスタ(外食)が9.4%、ビール(外食)が10.2%、コーヒー(外食)が10.9%と値上げ幅が低かった。ここでも飲料に関係する外食にはお得感があった。この一般外食の場合、コストの中に店員などの人件費の占める割合が高いので、値上がり率の高い食材コストの影響が相対的に薄まっていると考えられる。