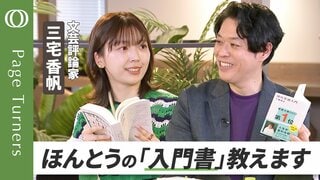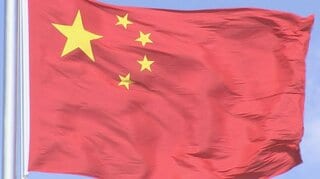人員を不足している企業へ…「労働移動」の課題は?
企業にとって、賃上げをしようというときに問題になるのが、潜在的な余剰人員である。AIなどの技術を活用すると、社内失業が生じる。社内失業を抱えたままでは企業の生産性は上がらず、賃上げにつながりにくい。自然減で対応すると、賃上げのスピード感は当然ながら落ちる。9月の自民党総裁選挙では、解雇規制の緩和が話題にされたが、この問題意識は生産性のネックになっている点で重要だ。企業が解雇せず、人手不足の他社に余剰人員を速やかに移動させる経路を太くしなくてはいけない。そうした対策を政策的に論じる必要がある。筆者としては、在籍型出向や転籍を増やし、生産性上昇の工夫が賃上げにつながりやすい流れをつくるべきだと考えている。
この余剰人員と対照的なのは、中小企業の人手不足だ。事業拡大をしたくても、ハローワーク経由では欠員を埋めにくい。もしも、大企業などに余剰人員が多く滞留しているのであれば、職種の変更をして、自社にほしいと思っている。大企業の余剰人材の中で、まだまだ現役で活躍できそうな人は多くいるはずだ。このルートを開けば、大都市から地方への人口移動にもつながり、石破首相の唱える「移住者を増やす」ことになる。大企業の余剰人員を、中小企業にマッチングさせることは、2つの問題を一挙に解決し、そこで地方移住も促進する対応を促せば、1粒で3度の効果が見込める。だから、石破政権は、各種の政策メニューの中での優先順位をよく考えて、解雇以外の労働移動の道筋についてももっと議論すべきだろう。
給付金・減税では限界…「物価対策」の議論もアップデートを
岸田前政権の時代は、エネルギー価格支援や各種給付金で物価高への対策をしてきた。しかし、その効果は限定的なものだった。むしろ、賃上げ促進や株価上昇を通じて、家計の所得増を間接的に支えてきたことの方が評価できる。だから、石破政権が賃上げ促進と資産所得倍増計画を引き継ぐことを表明したのは合理的選択である。たとえオリジナリティが欠けると言われても、物価上昇の弊害を緩和できるのだから萎縮する必要はない。問題は、賃上げ促進をバージョンアップできるかどうかだ。分配ではなく、生産性上昇の測定や労働移動のところまで拡張できるかどうかが問われる。
野党にも言えることだが、バラマキ的な手法はやっている感はあっても、効果が一時的で範囲も狭い。エネルギー価格支援補助のように、一度始めたならば、それを止めることも容易ではない。野党には、政権担当能力を示すためにも、バラマキ的でない手法を提示してほしい。
国民の側でも、与野党の実効性の低い政策の有無に一喜一憂するのではなく、与野党のいずれの政策が賃上げ促進に対して実効性があるのかに注目しなくてはいけない。物価対策の議論の質も同様に、バージョンアップしてもらわないと困るというのが、政策ウォッチャーのエコノミストの意見である。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生)