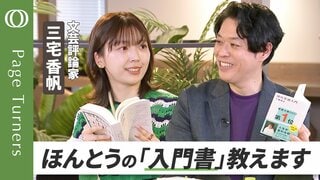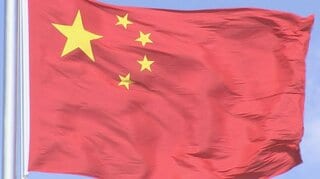物価対策の切り札は…「日銀の金融政策」
食料品とエネルギーは、輸入価格の高騰の影響を受けやすい。食料品は、食糧自給率が38%だから、約6割は輸入に依存していることになる。一次エネルギーでは、9割が輸入に依存している。つまり、輸入価格を下げることができれば、食料品+エネルギーのコスト高を抑制できる。具体的には、日銀が追加利上げを進めて、為替レートを円高にすると、輸入物価は引き下げられる。物価対策の切り札は、日銀の政策なのである。
しかし、この利上げは政治的に嫌われる。企業の利払い負担を増やし、株価にもマイナスだからだ。政府債務も増えて、歳出制約も高まる。経済学では、物価と景気にトレードオフの関係があり、利上げは景気に犠牲を強いることが知られている。日銀による物価対策は、誰かの利害を脅かさずにそれを実行しにくいところが政治的な難点だ。石破政権にとっても、物価対策として金融政策を前面に出しにくい背景なのだろう。
そうなると、日銀の追加利上げは景気がより改善することを前提にして、それと同調してゆっくりと進めるしかない。現在の日銀は、2026年度までの経済物価シナリオを想定して、そのシナリオの通りに着地しそうであれば追加利上げをするスタンスだ。このことは、景気と物価のトレードオフを念頭に置き、景気に過度のストレスを与えないための基準にもなっている。
カギを握る「賃上げ促進」の行方
日銀が、景気と物価のトレードオフを気にして慎重な利上げに徹したとしても、まだ物価が割高だという不満は国民には残る。黒田総裁時代に打ち出された2%の物価目標がそもそも高すぎるから、国民の不満が生じるのかも知れない。
それを脇に置いておくとして、次に必要なのは、生産性上昇を通じた賃上げである。生産性上昇には物価抑制の効果もある。難点は、それが目に見えて進捗しているとは確認できないところだ。例えば、GDP統計のような指標で、四半期ごとの労働生産性が上下動していることが「見える化」されていればよいのだが、現実はそうなっていない。
また、経済学では「賃金の粘着性」ということも言われる。賃金は一旦上げると下げにくいという傾向のことである。企業は、たとえ生産性上昇が進み企業収益が厚みを増したとしても、即座に賃上げをしないのは、この粘着性があるからだ。それが生産性が上がったとしても、賃金は敏感に上がっていきにくい傾向を生み出す。この辺の障害にどう対処するかは、これまで政策的にほとんど議論されたことがない。「生産性が大切だ」と言うのならば、もっと基礎的な指標を完備して、生産性に見合った賃上げがマクロ的にできているかどうかを企業の外からチェックした方がよい。
さらに、春闘などで賃金が上がっても、それに連動しない労働者が多くいると、賃上げは不十分という声が高まる。石破首相が2020年代に最低賃金を1,500円以上に引き上げようと主張するのは、この格差への配慮を念頭に置いたものだ。筆者は106万円や130万円などの年収の壁も、最低賃金を引き上げるのに併せて議論しないと意味がないと考える。年収の壁は、基礎控除額などを物価連動で引き上げる方法もあると思うが、これも政治的には好まれない。最低賃金の議論は、そうした包括的なかたちで進まないと成果を上げにくいと考える。