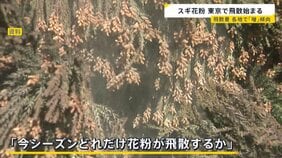前歴の開示と前歴者の就業制限の検討も
子どもの性被害に詳しい千葉大学大学院の後藤弘子教授はこう語ります。

千葉大学大学院 後藤弘子教授:「性加害をする教員は指導力がある人も少なからずいるなかで、加害者を見分けるのはかなり難しい。1件の被害申告があったということは、初めてこのような行為をしたとは考えにくく、以前からいやな思いをしている子どもがいた可能性はある」


偏見を持たずに、ささいな違和感に気づく“目”を学校全体で育てる努力が大切だといいます。
千葉大学大学院 後藤弘子教授:「犯罪履歴のチェックを行ったとしても、それで防げるのは今起こっている性暴力のわずかにとどまる。多くの性被害は学校現場の不断の努力が行われない限り減らないと思うし、なくならないと思う」
4月1日からは、子ども政策の司令塔となる「こども家庭庁」が設置され、子どもの権利を守るための総括的な「こども基本法」が施行されます。子どもの性被害防止についても、子どもへの性犯罪歴のある人が教育や保育の現場で働くのを制限する「日本版DBS」の導入も検討されています。
DBSとは、イギリスで行われている前歴の開示と前歴者への就業制限機構「Disclosure and Barring Service」の略で、これを手本に日本版が検討されています。きっかけは、2020年にベビーシッターの男が、保育中の子どもに対する強制わいせつ事件で逮捕されたことでした。被害にあった男児は20人に上るとされています。

後藤教授は、日本では子どもの権利は手厚く守られるべきだとしたうえで、新しい法律ができていることを、外国人の教員にも、研修や学校ごとの教育できちんと伝えるべきだとしています。また、自治体の教育委員会などについても、万が一、被害が発生した場合に備え、時系列で誰がどう対応するかといったマニュアルを作成するなど、きちんと制度化する必要があると指摘しています。