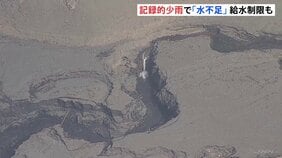およそ800年にわたり、地域の火伏せを祈願するまつりとして受け継がれています。宮城県登米市で6日、稲わらをまとった男性らが家々を回りながら水をかけて防火を願う「米川の水かぶり」が行われました。
登米市東和町の米川地区も6日朝は雪が積りました。地元に住む11歳から61歳までの男性21人が、火の神の化身となるため稲わらを身にまといそれぞれ自分の顔に煤を塗っていきました。
参加した人:
「この地区のために安全のために頑張る」
そして、厳しい寒さのなかまちに繰り出しました。800年以上続く「米川の水かぶり」は、毎年2月の「初午」に行われている、国の重要無形民俗文化財です。2018年にはユネスコの無形文化遺産にも登録されています。

男性らは、奇声を上げながら沿道に用意された桶に入った水を家々にかけて回り、地域の防火を祈願しました。また、住民らは男性たちがまとった稲わらを防火のお守りとして持ち帰ろうと抜き取っていました。

岩手県から訪れた人:
「1年に1回(稲わらを)もらい、火災にならないようにしたい。いっぱい取ったのでみんなに福を分けたい」
地元住民:
「ずっと続いているので、これからも続いてほしい。火伏せなので、災害もなく過ごせたらいい」
沿道には、大勢の見物客が訪れ火伏せのまつりを楽しんでいました。