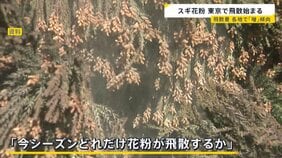東北大学などが宮城・岩手の住民を対象に行った調査で、東日本大震災による住まいの被災程度と死亡率に関連性がみられないことが示されました。

東北大学は、自治体などの公衆衛生への取り組みが住まいの被害が大きかった被災者の死亡リスクを抑制した可能性があると指摘しています。
東北大学と岩手医科大学は、2013年5月から2021年12月まで、宮城と岩手の住民5万8000人余りを対象に追跡調査をし、震災時の住まいの被災状況と死亡リスクの関連性を調べました。

その結果、住まいの被災程度と死亡率には関連性が見られないことが分かりました。
東北大学東北メディカル・メガバンク機構 中谷直樹教授
「家屋被害の程度が大きい方では被害がない方に比べて、中長期的な死亡リスクが高くなるのではないかという仮説を持っていた」
今回の調査結果で関連性が示されなかった要因について東北大学は、震災後の医療サポートや公衆衛生の取り組みが、住まいの被害が大きかった被災者の死亡リスクが高まることを抑えた可能性があると指摘しています。
東北大学東北メディカル・メガバンク機構 中谷直樹教授
「当時、避難所の体育館に集まって、医師がいろいろなサポートや薬の提供など医療態勢を一生懸命頑張った。各自治体の健康増進などいろいろな授業があって自治体の方も頑張った。さらに被災者には、医療費の免除などもあった。医療へのアクセスが高くなって、しっかり治療ができたのでは」
東北大学は、被災者の健康状況などについて追跡調査を継続し、災害発生時の健康被害を減らすことにつなげたい考えです。
大規模な災害による住まいの被害と死亡率の関連性の研究では、今回の調査は対象者数や追跡調査の期間など世界的にもこれまであまり例のないトップレベルの規模だということです。