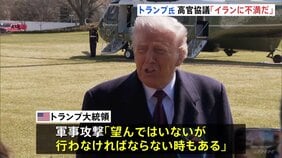御用船の難破が縁で生まれた日本を代表するスイーツ
このように、自然環境から共通項が多い静岡県と鹿児島県ですが、歴史にも深い繋がりがあります。寒くなるとつい手が伸びてしまう「干し芋」。薩摩芋を蒸して乾燥させただけの食べ物ですが、素朴な甘味とねっとりとした食感が人気でコンビニなどでも気軽に買うことができる“スイーツ”です。現在は茨城県が国内生産量のトップですが、その発祥は静岡県です。
1766(明和3)年、御前崎沖で遭難した薩摩藩の御用船「豊徳丸」の乗組員を、地元の組頭、大澤権右衛門と付近住民が助けたことをきっかけに静岡県に薩摩芋が伝来します。当初現金をお礼に差し出されましたが大澤は「難破船を助けるのは村の習わし」と断ります。それではと、薩摩藩側は当時、藩の特産品で栽培方法は門外不出と厳しく管理されていた薩摩芋3本と栽培方法を大澤らに伝えました。
砂地だった御前崎近辺は薩摩芋の栽培に適していて、すぐに薩摩芋の産地となりました。大澤はその功績が認められ「いもじいさん」の名称で広く愛され、御前崎市の海福寺に供養塔が立てられています。
その後、保存のために薩摩芋を煮て包丁で薄く切ったものを天日で干す「煮切り干し法」が考案され、これが「干しいも」の始まりとされています。天日干しすると甘さとやわらかさがより増します。この地域特有の冬に吹く偏西風「遠州からっ風」と長い日照時間は、干し芋の生産に適していたようです。
人命救助が縁で鹿児島の農産品が静岡に伝わり、保存のための工夫が人気スイーツとして静岡から日本中に広がりました。