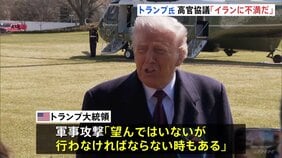先鞭つけた静岡の養慢技術、環境生かした鹿児島
緑茶以外で静岡と鹿児島に共通するのが養鰻です。2022年、静岡県は2365トン、鹿児島県は7858トンのウナギを生産しています。ウナギ養殖発祥の地といわれる静岡県では温暖な気候、豊富な地下水を生かし、1891(明治24)年に原田仙右衛門が湖西市で、服部倉治郎が、97(明治30)年に浜松市西区舞阪町で養鰻をスタートさせました。以来「ウナギといえば静岡」と全国にその名が知られるようになり、数多くの養殖に関する技術も静岡から発信されました。

現在、国内シェアの約40%を鹿児島県が占めています。中でも日本最大のウナギ養殖産地として知られるのが大隅半島。1972年に大隅地区養鰻漁業協同組合が設立され、南国特有の温暖な気候に、シラス台地に育まれた良質な地下水という、静岡と似通った環境を生かして養慢が盛んに行われています。