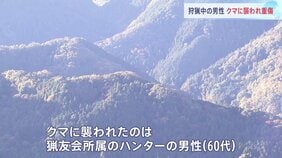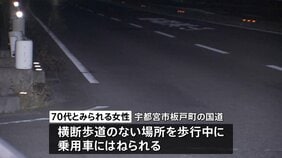2024年8月、初めて発表された「南海トラフ地震臨時情報」。「社会がどう理解したのか」「国の責任があいまいだったのではないか」。教訓を踏まえ、いま専門家たちが課題を指摘しています。
<南海トラフ地震評価検討会 平田直会長>
「少なくとも東海地域については予知されるということが前提でしたから、予知されると、象徴的に言うならば新幹線を止めるというような非常に厳しい規制をやっていました。しかし現在は、それは予知できないんだから厳しい規制はないよと。基本的には自主的な対応にしなさいよということは国が決めたわけです。で、これはなかなか難しいです」
2024年10月、新潟市で開かれた日本地震学会です。2024年8月、初めて発表された「南海トラフ地震臨時情報」について、専門家がさまざまな立場で課題を投げかけました。
8月8日、宮崎県沖の日向灘で発生したマグニチュード7.1の大地震。気象庁は南海トラフ地震の想定震源域で、大規模地震が発生する可能性が普段より高まっているとして、臨時情報の「巨大地震注意」を発表しました。
国が呼びかけたのは「日頃からの地震への備えの再確認」。
東海道新幹線が速度を落として運転したり、一部の海水浴場が閉鎖されるなどしました。しかし、具体的なことはそれぞれのリスクに応じて考えなければならず、地域によって対応はばらばらでした。
<南海トラフ地震評価検討会 平田直会長>
「重要なのは、脆弱性が高いとか、低いとかというのは国が決めるのではなくて、基本的には自分で決めなさいよと。ここが難しいところです。しかし、ここが最も重要なことだと私は思っています」
南海トラフ地震評価検討会の平田会長は不確実性がある臨時情報について、その意味を社会がどう理解して防災行動が取られたのか。今後、調査と議論が必要だと話しました。
一方、国民や科学者に判断を丸投げした国の対応を疑問視する専門家もいます。指摘するのは臨時情報が発表された8月8日の夜、官房長官の会見です。
<記者>
「どれくらいの期間を想定すればいいのか、その間の国民の対応について、具体的な呼びかけがありましたらお願いします」
<林芳正 官房長官>
「南海トラフ地震臨時情報に関して気象庁から説明がなされるところでございますので、詳しくはそちらにお聞きをいただければ」
<松本大学 入江さやか教授>
「このあと、臨時情報については気象庁から説明がなされるところでございますので、詳しくはこちらでお聞きいただきたいと思います。言葉は悪いですが『丸投げか』という印象を持ちました」
政府としての価値判断をほとんど行わないなか、その後、始まった気象庁の会見。登壇したのは気象庁の担当課長と評価検討会の会長という地震学の専門家の2人だけでした。
<松本大学 入江さやか教授>
「防災対応に関する政府の正式な発信者、説明者がいないんです。このお二人だけなんです。本来であれば、防災行政の担い手、例えば内閣府防災の方がここにいらっしゃるべきだと」
記者からは「お盆の時期の帰省や海水浴に行っても良いのか」などと具体的な防災対応を問う質問が出ました。しかし、政府の防災担当がいかなったため、地震学の専門家が「個人的な見解である」と前置きをして答えざるを得ませんでした。
<松本大学 入江さやか教授>
「科学的評価から先、情報発信と結果責任は行政が負うことを明確にすべきではないでしょうか。次に臨時情報が出たときに、どなたが海水浴に行っていいですか、という問いに会見の場で答えるんでしょうか」
入江教授は「責任の所在があいまいなのは地震学者にも国民にとっても大変不幸なこと」だと締めくくりました。