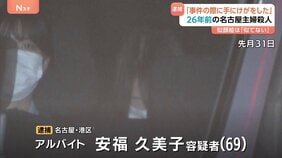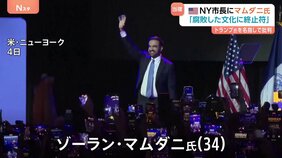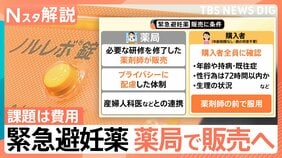5年前の台風19号災害では、地元の消防団が初期の避難や復旧作業で大きな役割を果たしました。
被災地で現場を指揮した団員が感じる課題とは?
そして子どもたちの防災意識を高めるため保護者が行っているプロジェクトを取材しました。
台風19号で大日向(おおひなた)地区の抜井川(ぬくいがわ)と隣りの余地(よじ)地区の余地川が氾濫した長野県佐久穂町。

土石流で家屋が押しつぶされ12戸が全壊するなどあわせて180戸が被災したほか、道路が寸断され護岸が崩れるなどの被害が相次ぎ、災害復旧工事は2023年の3月まで続きました。
当時、初期の避難や復旧作業などで大きな役割を果たしたのが消防団でした。
「あれ抜井川なんですけど」
被災した大日向と余地地区を管轄する第3分団の分団長を務める倉澤享志(たかし)さん。
5年前も副分団長として現場の指揮をとりました。
倉澤さん:
「あそこが一番被害がひどかった集落になるんですよ。水があふれ出てこっち側の田んぼ、家、床下浸水して」
台風が集落を襲った12日の夜、まず行ったのが避難誘導です。
およそ90人の分団員のうち50人ほどが出動し、川の近くに住む人や一人暮らしの高齢者などの家々を回り避難を呼びかけました。
倉澤さんが住む家もライフラインは寸断。
家族を避難所に残して現場に向かったといいます。

倉澤さん:
「使命感、責任感、自分の生まれ育った地域ですし、地区で暮らしている人の顔も全員わかりますし、あそこの家はあのおじいさん動けなかったなというのもわかるので、動ける自分たちが動かないといけないという。逆に言うと生まれ育った地域だからこそわかるというのもあるんですけど、そうだあの家おじいさんだけだったなとか、あそこのところ確か昔も崩れたよなとかっていうのも」
2日目に行ったのが、被災箇所の調査です。
倉澤さん:
「ちょうどここ今、新しくなっているところが全部道路が(川で)削り取られて落ちた。被害が出ているところを確認しながら地域を全部ぐるっと回って(災害対策)本部にあげる感じで9割以上の情報収集を消防団で担っていました」
3日目から復旧作業が始まりました。
倉澤さん:
「この上から流れてきて、ここの通りの家が土砂で埋まってしまったんですよね」
家屋に入り込んだ土砂の撤去や家財道具の片付けなど、ボランティアセンターが立ち上がるまでのおよそ1週間、作業が続きました。
倉澤さん:
「実際自分が体験したことで他人事じゃない、いつどこで誰が(災害に)あうかなんていうのはもうわからないことなんだと。そのためにどうするっていったらやっぱり防災意識高めるしかない」