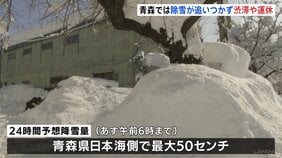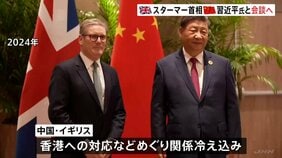2人の研究は、キャベツの搾り汁と活性汚泥を混ぜ合わせ、そこに酸素を送ります。
活性汚泥の中の微生物の働きによって有機物が取り除かれると、透明に近い液体に。
これが肥料となります。
この液体肥料を10日間、豆苗(とうみょう)に与えて栽培したところ。

渡邉さん:
「青いグラフが(豆苗の)長さで、オレンジ色のグラフが重さを表しているんですけども、水道水よりも(廃棄野菜から作った)液体肥料を使ったものの方が、重さも長さも上回るという結果が得られました」
廃棄野菜と微生物による肥料作りは、コンポストなどでもよく見られますが、完成までに時間がかかります。
渡邉さん:
「私たちの実験(肥料作り)が、30分から7時間ほどで終わるものが、コンポストは50日ほどかかってしまうので、短時間で効率的に行う液肥化というものに関しましては、私たちが作ったこの液体肥料の方が、よりよい液体肥料だったと考えられます」
生産者が丹精を込めて育てた農作物。
自然災害にあっても、野菜を廃棄することなく別の形で有効活用したいと、2人の研究は始まり、コロナ禍での休校などの影響で牛乳の廃棄が問題になったときには牛乳で肥料作りに取り組みました。
さらに、信州ならではのリンゴを使った肥料作りの研究も進めています。
清水さん:
「リンゴは活性汚泥を用いて肥料にしていない原液も、水で育てるよりも成長したという面白い結果が得られました。この原因についてはまだわかっていないので、どうしてそうなったのかというような探究もしていきたい」

清水さん:
「今回はリンゴ・キャベツ・牛乳に着目したんですが、例えばイモの葉っぱなども有効活用できるのかという探究も続けたりとか、微生物にも着目して学びを続けていけたらなと思っています」