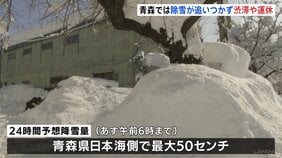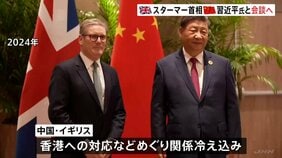松本県ケ丘高校の自然探究科。
実験や観察などを通じて自然科学の分野を中心に学習を深めています。
この自然探究科の3年生2人が、自然災害などで廃棄される野菜を有効活用したいと、ある研究に取り組んでいます。
女子高校生2人:
「こんにちは」
「お願いします」
松本県ケ丘高校自然探究科3年の清水結月(しみずゆづき)さんと渡邉咲奈(わたなべさきな)さん。
2人は自然科学分野で信州が抱えるさまざまな課題とその解決策を研究しています。
渡邉さん:
「私たちは『廃棄食品』の有効活用をテーマに探究してきました」
その研究成果がこちら。

渡邉さん:
「廃棄野菜で作るエコな肥料です」
エコな液体肥料、その作り方です。
まずはミキサーを使ってキャベツを細かく刻み…。
そして、搾って出てきた水分を使います。
清水さん:
「私が小さい頃にお父さんが餃子をよく作ってくれたんですけど、お手伝いした時にキャベツを刻んで水分を搾って入れていたんですけど、この水分がもったいないなって、なんか有効活用できないかなっていうので発想を得ました」
しかし、キャベツの搾り汁だけでは肥料になりません。
清水さん:
「そこで私たちが着目したのは『活性汚泥』といって、私たちはここに廃棄食品とかを入れて肥料を作ることをしました」
「活性汚泥」は、主に下水処理で使われている微生物の集合体です。
小学生の頃の下水処理施設見学で学んだ浄化方法から、微生物の力を肥料作りに生かすアイディアが浮かびました。

渡邉さん:
「植物が育つのに必要な成分には窒素・リン酸・カリの3つがあるのですが、これらの成分っていうのは既存の肥料に含まれているんですけれど、活性汚泥を混ぜることで同様にこれらの成分が多く得られるのではないかと考えました」
2人の研究のため活性汚泥を提供したのが、安曇野市と松本市の一部地域の下水処理を行う「アクアピア安曇野」です。
活性汚泥は下水の汚れを取り除く重要な役割を果たします。
アクアピア安曇野を管理する県犀川安曇野流域下水道事務所 高橋知之さん:
「活性汚泥というのは有機物の汚れを多く抱え込んだ生きた微生物の塊のことです」
高橋さん:
「活性汚泥に含まれている生きた微生物が汚れを食べて水を浄化しているところになります」
宮入キャスター:
「ブクブクしているのはなんですか?」
高橋さん:
「空気を送っていまして、微生物も生き物ですので、空気を送ることで活性化されて、より汚れを食べてくれるということになります」