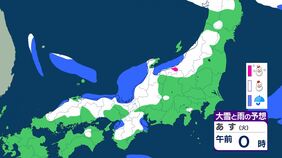この日は、プログラムに協力する信州大学教育学部の三和(みわ)准教授と、メタバースで待ち合わせしてもらいました。
轟博和さん:
「三和先生、こちらに来てもらえますか」
「こんな感じで挨拶をして、今日何しようか、あっちに行ってみようかとか」
鬼ごっこをしたり、ブロックで家を作ったり…。
ビデオ通話で参加者とコミュニケーションをとりながら、一緒に時間を過ごす。
家に引きこもりがちになっている子どもたちにとっては、これも大きな一歩です。

轟博和さん:
「オンラインの世界から、外の世界への中間、接続になるようなハブ的な場所になってほしいなと」
子どもたちを見守り、支える大事な役目を担うのが、信州大学教育学部のボランティア学生たちです。
オープンを前に、自分たちの名札づくり。
ボランティアの学生:
「まじめな感じと、こういう楽しい人だと思ってもらうといいなと」

顔写真のほかに、ニックネームやイラストを入れて、親しみやすいよう工夫します。
信州大学教育学部からは、およそ80人の学生が、ササフレンドとしてササランドの活動に参加。
そのほとんどが有志です。
信州大学教育学部 茅野(ちの)理恵准教授:
「いよいよササランドでの活動を開始するにあたって、きょうはササフレンドガイダンスということで」
ササランドの立ち上げから関わる教育学部の茅野准教授は、親でも先生でもない「大学生」ならではの感性が大切になると話します。
茅野准教授:
「一緒に遊ぶことが純粋にできる」
「どうしても大人の方が子どもに何かさせるという視点でいろんな活動を見てしまうけれど、学生はおそらく自分が楽しむことに自然と巻き込む」
コロナ禍で子どもとの直接的な関わりが制限されていた学生にとっても、将来に繋がる貴重な経験です。