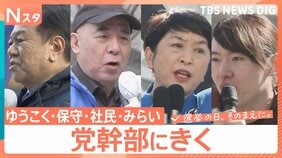長崎県の諫早湾干拓事業で堤防の排水門の開門をめぐり、長年続いていた法廷闘争は、「開門しない」ことで事実上決着しました。農家と漁業者、それぞれの利害が対立する問題で、決着後も波紋が広がっています。
◆矛盾する判決「司法のねじれ」

一連の裁判では開門を求める漁業者側と、門を開けないよう求める営農者側がそれぞれ国と争っていました。2010年に開門を命じる判決が出され、これを当時の民主党政権が上告せず、判決が確定しました。一方、2013年には営農者側の主張を認めて開門の差し止めを命じる決定が出され、司法判断がねじれた状態となりました。
自民党政権となった国は開門を命じた確定判決の無力化を求めて裁判を起こしました。その後、国は「開門によらない基金による和解が最良」との立場で、両者の和解を目指しましたが、話はまとまりませんでした。
そして3月1日、開門を命じた確定判決の無力化を求めた上告審で、最高裁判所は漁業者側の上告を棄却する決定を出し、開門命令の無力化を認めた判決が確定しました。
◆“水門を開けて欲しい”漁業者

これでねじれていた司法の判断が「開門しない」ことで事実上決着したのです。ギロチンと呼ばれた鋼板で湾が閉めきられてから26年。法廷闘争の決着に漁業者、営農者はどう受け止めているのでしょうか。
佐賀県川副町の川崎賢朗さん(62)。親子3世代でノリ漁師をしています。諫早湾の排水門を開門しないことで事実上決着したきのうの最高裁決定に憤りました。
川崎賢朗さん「がっかりっていうか、悔しいですよね。憤りを感じています。政府はなめてますよね。裁判所を。裁判所もこういう判決をだすんだから、裁判所の意味がない。そこまで言いたくなりますよね。どこを信じていいのか弱い人間ですね」
開門を命じた判決が確定したにもかかわらず、それを裁判で無力化するという国のやり方に苦言を呈します。今年は記録的なノリの不漁に陥っていて、海の異変と開門調査の必要性を訴えます。
川崎賢朗さん「今年は雨が少ないうえにプランクトンが居座ったと状況をみると完全におかしな海になってしまったのかなと。有明海のこの現状を見ると、開門調査が必要だと思っていましたし、最高裁もそんな判決が出してもらえるのかなって思っていました」
漁業者側の弁護団は「憲法史上初めて確定判決に従わなかった国を免罪し、司法本来の役割を放棄したものと言わざる得ない」「有明海再生に向けた開門と開門調査は不可欠で、紛争解決のための話し合いの実現を広く呼びかける」との声明を出しました。