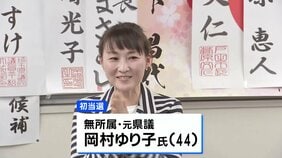◆植松死刑囚に関する8つの「仮説」

出版を記念した講演会が2月11日、神奈川県相模原市で開かれました。聴衆として上京したのですが、私の名前の張り紙が壇上にあり、いきなり事務局が「しゃべれ」と。びっくりしましたけど、それはさておき、佐藤さんはこんな風に語りました。
佐藤幹夫さん:事実関係に関しては、記者さん方が最初から非常に取材を旺盛にされていたので、その事実に付け加えるような取材はちょっと難しいだろう、と。どうやって自分の書いていくものを差別化していくかと考えた時に、例えば例えば――。
・なぜ被害者の方が、遺族の方が匿名になったのか。そこにはどういう問題があるのか? なぜなのか?
・やまゆり園でも、自分たちのやっている支援について振り返って、そこで掘り下げて、何かメッセージを発信してくるということをしてもらえない。施設の持っている問題も、しっかりと掘り下げて考えていく必要はあるんではないか。
・一体あの裁判が、どういう裁判で、何がそこで話し合われたか。どういうものだったか、しっかりと今までみんなに提示できていたのか。
・それから、植松死刑囚。彼がしゃべっていた、優生思想のこと、大麻のこと、障害者のこと、いっぱい書かれ語られているんだけれども、むしろ大事なのは、彼が「語ることを拒んだこと」「語らなかったこと」ではないか。そちらの方に、この事件を考える非常に重要なヒントが隠されているんじゃないか、と。
佐藤さんはこの本で、8つの「仮説」を説明していきます。
仮説1:植松死刑囚は、重要なことを話していない。不必要なことを語りすぎるし、重要なこと話さない、という傾向が見える。したがって、彼の語ることを真に受けてはいけない。何らかの「裏読み」や「深読み」が必要になる(243ページ)。
僕ら記者は取材して、相手が何と語ったかを伝えていくわけですが、「語らなかったこと」を探ろうと取り組んでいるわけです。
◆養護学校教員だったからこそ書ける「仮説」
8つある仮説からもう一つだけ紹介します。「怒りと憎悪と、被害感情が反転した攻撃感情」を佐藤さんは挙げています。

佐藤幹夫さん:重度の障害を持っている方たちだからこそ、身の回りで世話をしている支援者がどういう人間か、とても敏感に察知するんだと思うんですね。
(植松死刑囚は)「しつけで、鼻先を小突いた。それは犬や猫をしつける時もそうやってきたから。人間の場合も同じなんだ」と言っている。そういうことを考えている人間に、利用者が心を開くわけはない。絶対反抗しますよ。服を脱がせようとすると嫌がる。ご飯を食べさせようとスプーンを出すと顔をそむける。彼らなりのやり方で、いろいろな形で反抗していく。絶対、言うことを聞かない。
そうすると植松聖支援者は、非常に自分のプライドが傷つく。「この野郎」と思う。自分の受けた仕打ちを、利用者さんに返していく関係になってしまう。そうすると、あとは一直線ですよね。周りの支援の仕方がすごく気になる。
佐藤さんは養護学校の先生だった。だからこそ「支援者」の視点を持つ。本で、こうも書いています。
「障害をもつ人との感情交流」という、支援職員としてまずは身につけるべきスキルを、ついにもてなかった、もとうとしなかったということを示しています。決して、「障害」をもつ人たちが「何もできない」ゆえに、ではありません。「何もできない」のは、植松容疑者自身の方だったのです」(59ページ)
確かにそうだろうと思います。