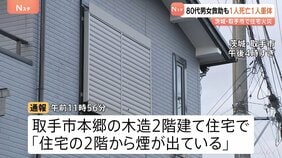最初の授業でいきなり変化が
引き受けた寮さんはとにかく「最初は絵本をみんなで読もう」と。登場人物の役柄ごとに、線を引いて「ここだけ読めばいいから」と言って、みんなで読んでもらう。ガタガタでうまくいかず大変だったそうです。ところが突然、みんなで合わせてしゃべろうという動きが始まりました。最初の授業で、寮さんは本当に驚いたそうです。

寮:全部ひらがなで書いてあって、2~3行とか4行とか大した行数はないんです。前に2人立ってもらって、みんなも床の上に座ってこっちを見ているんですけど、「大丈夫かな、読めるかな、読めるかな……」、最後のページまで行くとみんなホッとして「よかったねー!」って盛大な拍手が湧くんですよ。初めて行った授業の最初の1時間目の、その瞬間でした。いきなり変化が、始まった。いきなりですよ。
寮:「緊張したけど、読めてよかったです」とか、「拍手もらって、うれしかったです」と。最初はみんなちょっと下向いて「やりたくない」って言っていた子がだんだんやりたくなってきて、最後の方になると「次、誰やりますか?」って言うと「はい!」って自分から手を挙げるわけですよ。最初のアウェー感と全然違う空気感になっているんですよ。たった1時間半、初対面の授業で。「すごいな」と思って。
これは、寮さんの実体験です。刑務所の職員も「一体何をしたんですか?どうしてこんなことが」と言ったそうです。寮さんが何かしたというより、彼らの中にもあるものが引き出されてきたという感じだったんだろうと思います。
警察に捕まった時の「詩」

寮:だいぶリラックスして楽しくなって、仲間感ができたところで、ここまでが心の準備体操。ここからは「それじゃあ、宿題で詩を書いてきてね」って言って。そうすると「先生、宿題って何ですか?」聞いたら、小学校にも行かせてもらえなかったから、宿題って言葉も知らないんです。
寮:「上手な詩、いい詩を書かなくてなくていいんだよ、立派なことを書こうと思わなくていいんだよ。もうつぶやきでもいいし、何でもいいんだよ」って言って、一生懸命ハードルを下げて。どうしても書くことがなかったら、好きな色について書いてちょうだいっていうお題を出したの。
寮:でも教官が「書くことなかったら『書くことがない』って書いてきてもいいんだぞ」と言うから、「余計なこと言って!」と私は思って。そうしたら、全員「書くことがない」「わからない」「見つからない」とか書いてきた。「来週は書いてきてね」って言ったら、みんなちょっと「寮先生かわいそう」とか思って、同情して書いてきてくれたの。そうしたら1人だけ「書くことが見つからない第2弾」って書いてきて。おちょくられているのかなと思ったけど、次の時間に突然書いてきたんですよ。「涙」っていう詩で、この子が警察に捕まったときの話を書いたんですね。
「涙」
仕事一本
ガンコな父
名前で呼ばれたことも
なかったから
必要以上
会話すらない
そんな関係である
ある警察官は
僕の父に質問をしました
「子どもを
漢字一文字でたとえると
なんですか?」
まっ白な紙に
大きく
大きく
書かれた文字は
「宝」でした
そのときぼくは
おさえられない
なにかを感じました
数秒後には
キレイな涙が流れていました
寮:ガーン。いい詩でしょ!? 私はこれを読んで、泣いちゃいました。
グッと来るところがありますね。「キレイな涙が流れていました」なんていう文章を書けるのか、と思いました。
「好きな色」についての詩
「好きな色について書いてきてもいいんだよ」と呼びかけた寮さん。「金色」と書いた少年がいます。
金色は
空にちりばめられた星
金色は
夜 つばさをひろげ はばたくツル
金色は
高くひびく 鈴の音
ぼくは金色が いちばん好きだ
少年受刑者が書いた実際の詩なのです。色についてなら、書きやすいかもしれません。その中で一番衝撃的だったのは、たった1行の詩。「くも」というタイトルです。
空が青いから白をえらんだのです
これは本当に驚きだったようですね。人に傷を負わせているけれど、自分も傷を負っているわけです。生まれたときから育ってきた過程で、いろいろなことを考えるようになっていく、変化が生まれてくる。少年が書いた詩は、『空が青いから白をえらんだのです 奈良少年刑務所詩集』(新潮文庫、税込み605円)として書籍化されています。
また、その経緯を書いたノンフィクション作品が『あふれでたのはやさしさだった 奈良少年刑務所 絵本と詩の教室』です。
『あふれでたのはやさしさだった 奈良少年刑務所 絵本と詩の教室』(西日本出版社、2018年、税別1100円)
奈良少年刑務所で行われていた、作家・寮美千子の「物語の教室」。絵本を読み、演じる。詩を作り、声を掛け合う。それだけのことで、世間とコミュニケーションを取れなくて罪を犯してしまった少年たちが、身を守るためにつけていた「心の鎧」を脱ぎ始める。
「罪を犯したのだから隔離しておけばいいじゃないか」という話ではなく、その子たちは社会に必ず戻ってくるのです。そこを考えないと、私たちの社会はうまく維持できないんじゃないかと、読んで思いました。
◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)
1967年生まれ。毎日新聞入社直後に雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。ニュース報道やドキュメンタリー制作にあたってきた。やまゆり園障害者殺傷事件やヘイトスピーチを題材にしたドキュメンタリー最新作『リリアンの揺りかご』は各種プラットホームで有料配信中。