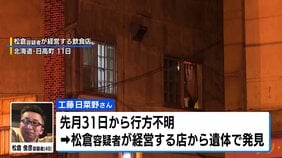メディアに課せられた姿勢
私も今、メディアを通じて話しているので自戒を込めて言うと、やっぱりメディアがそこに一緒になって大きく事件を報じているという問題があると思います。昔で言えば「夜討ち朝駆け」と言われて「スクープ取ってこい」ということを、ものすごく強要された時代がメディアの中にもありました。最近はそうでもないということは聞いていますけれども。
それと、警察発表をそのまま信じてしまう、そのまま報じてしまうきらいがあって、きちんと精査をすることなく、まず「これが悪いやつじゃないか」みたいなイメージをものすごく植え付けてきた装置であったこともあると思うんですね。
ですので、やっぱりメディアに出る側の人間とか、大きな情報を扱う側の人間が「疑われている人の人権とか人格を否定するようなことがあってはならない」というのが、自分たちに課せられている、メディア人として課せられていることかなと思います。
第2の袴田さんを出さないために
リスナーの皆さんにも考えていただきたいんですが、法学って勉強すれば、いかに抑制的に法を使わなきゃいけないかということを学ぶんですね。例えば、疑わしきは被告人の利益に、もそうですけれども、「なんかあいつ悪い奴、あいつ犯人や」みたいなことを短絡的に考えないようにしないといけないです。
例えば、メディアや警察発表の写真がものすごく嫌な顔をしているときを撮られていることがありますが、「いやいやちょっと待てよ」と。「この人、本当に何かやった人なんかな」というのを立ち止まって考える目というのを皆さんも養っていただきたいなと思います。
大川原化工機事件とか、いろんな事件が今でもやっぱり自白偏重のもと出されたものがありますので、そういったものに注目もしていただきつつ、一旦立ち止まって「この事件って何だろう」と考えていただきたい。
報じる側も、「ちょっと待てよ」と一呼吸置くみたいなところは非常に大事かなと思います。袴田さんのような方を今後出さないためには、ただ検察とか警察が悪いとかそういうことを言っているんではなく、私達市民が気をつけなきゃいけないこと、メディアの皆さんが気をつけなきゃいけないこと、いろんなことがあるんじゃないかなというのが今日のお話です。
◎谷口真由美(たにぐち・まゆみ)

法学者。1975年、大阪市生まれ。2012年、政治談議を交わす井戸端会議を目的に「全日本おばちゃん党」を立ち上げる(現在は解散)。元日本ラグビーフットボール協会理事。専門は、人権、ハラスメント、男女共同参画、女性活躍、性教育、組織論、ジェンダー法、国際人権法、憲法。