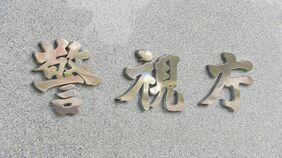「認定者と未認定者を区別する必要はなかったんじゃないか」
発言を遮られた形になった水俣病患者連合の副会長・松崎さんは、「大臣を恨むとかそんな気持ちはない」「とにかくみんなが救済されることが目的だから、別にそれ以外言うことはないんですよ」というようなこと怒りを押し殺しながら話しています。
松崎さん自身は水俣病患者に認定されておらず、亡くなった妻の悦子さんも未認定者です。でも、「国も県も認定者と未認定者を区別する必要はなかったんじゃないか」と、本質的なことを端的に訴えています。
不手際によるアナウンス効果という皮肉
水俣病と認定されているのは約3000人、一時金などの救済を受けた人は約5万人と言われています。それらに加えて、現在訴訟を続けている人は約1500人います。僕も不勉強で、今回のことで「そんなに(まだ)闘っているんだ」と認識を新たにしました。
医師の診断書をもらうことも難しいそうで、そういう現実があるということを今回の一件で知った方も僕だけではないと思います。そういう意味では、伊藤大臣および環境省職員の不手際のおかげで「アナウンス効果があったな」と、そうとでも思うしかないなという気がします。
解決に近づけるきっかけに
伊藤大臣は1日の懇談会で、団体側が発言を遮られるタイミングのときにも表情をあまり変えていませんでした。マイクがオフになってもその場にいた人たちは当然声が聞こえています。それなのになぜ「そのまま続けてください」という一言が出ないんだろう、そういうことを言えない人物が大臣をやっていることに、僕は恐ろしさを感じました。一般のコミュニケーションとしてあまりに不自然です。
問題が表沙汰になった後、伊藤大臣が再度水俣を訪れたわけですが、懇談会のときに「新幹線の時間がない」と言った人が1週間後謝罪に行くという、とんだ茶番です。
鹿児島空港に降り立って記者に囲まれたときに涙目になっていましたよね。その1週間前のあの無表情の大臣のことを思い出してみると、非常に趣深い。ちょっと嫌味で言っていますけれども。
そのときに彼が言ったこと。「水俣病というのは環境省が生まれた原点です」「いかにこのことを大切に思っているかをお伝えしたいんです」「ちゃんと環境省の責任者も厳重注意しましたから」と涙ながらに語ったんですが、まあ皆さん思っているでしょうが「どの口が言う」って思いますよね。
先に述べた通り、今回の問題は一定以上のアナウンス効果がありました。風化しかねなかった水俣病が未だ解決していないということがクローズアップされる機会になりました。改めて被害に遭った方、患者たちの満足に少しでも近づけるような解決のきっかけになるといいなと考えています。