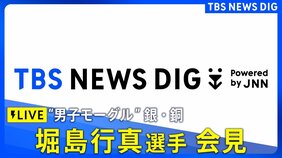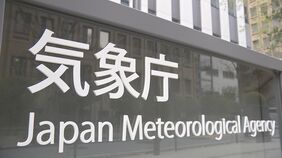沖縄戦で県民の運命を決めた作戦が練られた那覇市首里の第32軍司令部壕。現在、立ち入ることのできないこの壕の保存・公開を切望するのは、かつて平和祈念資料館を設計した男性です。
「戦争の実相を知る上で、戦跡の持つ意義は大きい」そう訴える男性の原点を見つめます。
平和祈念資料館を手掛けた男性 第32軍司令部壕への思い
おととし、首里城公園で行われた古式行列。琉球王朝時代の儀式を再現した恒例イベントです。この日は、首里城再建の起工式との同時開催とあって、多くの人が訪れました。

賑わいから少し離れた、守礼門近くの階段の下には、首里城が持つもう一つの側面に光をあててほしいと訴える人たちがいました。
建築家 福村俊治さん
「この壕の幅がですね、1m50から2m40くらい。本当に狭いところ。米軍は首里城の石垣が全部破壊されるくらい爆撃をしています」
建築家の福村俊治さん。自作の模型を使って説明するのは、第32軍司令部壕についてです。
旧日本軍が首里城地下に築いた第32軍司令部壕。牛島中将らによって、県民の運命を左右する作戦が練られた場所です。

現在は閉鎖されていますが、沖縄戦を象徴する戦跡として公開を望む声が上がっています。
建築家 福村俊治さん
「琉球王国という正の遺産、それと沖縄戦という負の遺産。これを一緒に将来に渡って伝えていくのは重要だと思うし。まず知ってもらうことが重要で、今日も沢山の方がいらっしゃって本当にありがたかったと思う」
浦添市に建築事務所を構える福村さん。手がけるのは、個人宅から都市計画まで。
建築家 福村俊治さん
「新しい模型なんですけどね。司令部壕って地下にあるものだからわかりにくいですよね。それを見てもらいたいと思ってこういう模型を作った」
隙間時間に行うのが、32軍司令部壕の公開に繋がる作業です。
事務所スタッフ
「仕事の合間合間で、まぁ私も手伝ったりするんですけど。それだけ、パワー・熱量があるのは凄いなと。沖縄戦に対する思いが本人にもあると思うので」

月に1~2回のペースで自作の模型の展示会を開催して、その継承の意義を発信。県内30か所以上を回ってきました。ただ100分の1スケールともなると、移動させるのも一苦労。
建築家 福村俊治さん
「あっち行ったりこっち行ったり。こんなに引っ越しが大変だとは思ってなかった。また本部でやるっていうから本部まで。難儀です」
展示会がない間の保管スペースは友人のガレージを借りるなど、どうにか確保している状況です。第32軍壕にこだわるワケ、それは過去の体験にあるといいます。