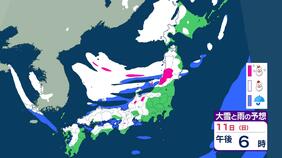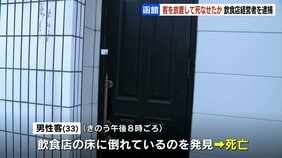これまで半世紀あまり無事故での不発弾処理を続けてきた陸上自衛隊ですが、今回の事故はどんな状況で起きたのか、説明は乏しいままです。専門家は積極的な情報開示を求めています。
▼名桜大学 大城渡 教授
「不発弾の発見から最終処理に至るまで、多くの関係機関が連携して関わるところに、不発弾処理行政の特徴があると思います」
不発弾処理の行政に関する研究をしている、名桜大学の大城渡教授。今回の事故について、陸上自衛隊の不発弾処理隊が、不発弾の種類を調べるために、さびを取る作業をしていたと説明している点に注目します。
▼名桜大学 大城渡 教授
「通常は安全化処理されているはずなので、そういった作業で爆発するということは考えられないはずなんですよね。だからその作業に原因があるというよりも、その作業を行っても大丈夫だと判断したその前提ですね」
県内で不発弾が発見されると、まず県警から自衛隊に処理が要請されます。
爆発の危険性を調査し、危険性が低い不発弾、もしくは安全化処理された不発弾が運搬される先が、9日事故があった一時保管庫です。

危険性が高く、動かせない不発弾を現地で処理をすることも、県内ではよくある光景です。
▼名桜大学 大城渡 教授
「今回の事故を受けて、改めて関係行政機関や住民間で、自衛隊が処理するものであっても、不発弾は危険なもので、自衛隊がタッチすればそれだけで一安心ではないと認識した」
この作業には、住民の避難や道路の通行止めなどに、自治体や消防など多くの関係機関の連携が必要となります。
しかし、不発弾の処理中に事故が発生した場合は、「関係機関で対策を協議する」とされていて、どう事故に対応するかや、責任の所在は明確ではありません。

大城教授はこうした現状認識に加え、関係機関から住民に対する情報公開が重要だと話します。しかし陸上自衛隊第15旅団は、今回の事故について報道機関に対する説明の場をいまだ設けていません。
今後、事故の経緯はどこまで説明されるのでしょうか。

▼名桜大学 大城渡 教授
「爆発事故が起こったということは、不発弾が多く発見される沖縄で県民の大きな関心事だと思うんですね。住民、県民の関心の高い今回の不発弾の爆発事故に関しては、自衛隊はメディアの取材、ひいては県民住民の知る権利に、十二分に答えていくべきだと思います」