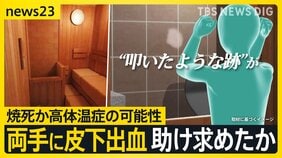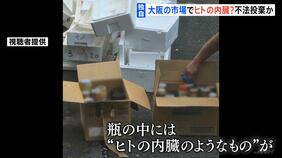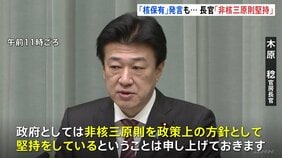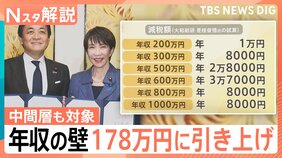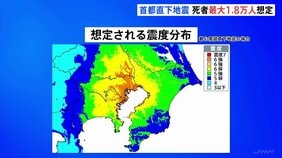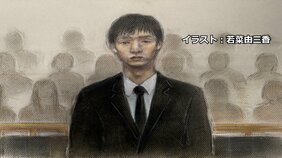1995年の阪神・淡路大震災では建物の倒壊により多くの犠牲者が出ました。あれから28年、思うように進んでいない住宅の耐震化やアーケードの老朽化など街なかにはいまだ多くの危険が潜んでいます。
高齢化で進まない住宅の耐震改修
阪神・淡路大震災から28年の17日。被災地、神戸の公園には多くの人が訪れ、犠牲者を追悼しました。
看護師の仲間を亡くした女性:
「28年もたったんだなとしみじみと思っています」
高校生の娘を亡くした女性:
「助けてあげられなかったのはやっぱり悔いが残る」
阪神・淡路大震災では建物の倒壊や火災などが相次ぎ、6434人が亡くなりました。このうちおよそ8割が倒壊した家屋による圧死が原因です。このため国は耐震改修を促進する法律を制定し、古い住宅などの耐震化を目指してきましたが、課題も残っています。

先週から耐震工事が始まった大分市内にある住宅。この家は1981年以前の旧耐震基準で作られており、「倒壊する可能性が高い」という診断を受けました。
カワノ・川野康雄会長:
「1階のバランスがとても悪くて非常にねじれやすい。住んでいる人は耐震性を心配していてこの結果をみて耐震工事に踏み切った」

耐震工事ではまず住宅を支える基礎を追加し壁の数を増やして家のバランスを整えます。それから金物を使って柱などを補強し耐震性を大幅に向上させます。改修には80万円を限度に工事費用を補助する制度もあります。しかし、国の調査では大分県内の住宅の耐震化率は84パーセントで、7万6000戸あまりの住宅が補強されていません。その理由について川野会長は「耐震改修が必要な住宅で年々高齢化が進み、意欲が低くなっている」と指摘します。
カワノ・川野康雄会長:
「関心は高まっているけど実際に行動に起こす人はまだ少ない。逃げられる地震の時は倒壊しない。(大地震は)まず動けないのでその不安感を取り除きたい」