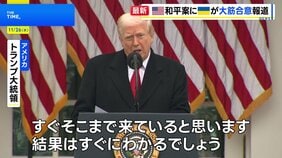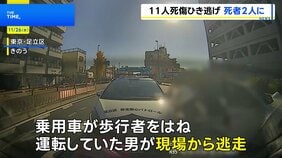大晦日、山形で大規模な土砂崩れが発生しました。こうした土砂災害の被害を防ぐための新たな取り組みが今、大分県内で進んでいます。
12月31日、山形で起きた土砂崩れでは高齢夫婦2人が亡くなりました。
県内でもこれまで各地で発生し被害をもたらしました。こうした土砂災害による被害を防ぐため県内で新しい取り組みが始まっています。
(県砂防課・岩田昇さん)「このあたりが土砂災害警戒区域に指定されていますので、こういった土砂災害警戒区域の標識を設置しております」
県が設置を進めているのが「土砂災害警戒区域標識」です。県内の土砂災害警戒区域は全国で7番目に多いおよそ2万4000か所。地元の住民だけでなくその地域を通行する人などにも注意を呼びかけ、迅速な避難につなげるのが主な目的です。
(岩田昇さん)「(県内には)約2万4千か所の土砂災害警戒区域がございます。こういったところに警戒区域があるんだっていうことを目で見て分かりますので、そういったことを目的に設置をしております」
取り組みのきっかけは2020年に神奈川で発生した土砂崩れです。マンション敷地の斜面が崩れ女子高校生(当時18)が亡くなりました。これを受けて、国は警戒区域の認知の向上を図る方針を策定。県内では来年3月までにおよそ9000か所に標識を設置する予定です。
(岩田昇さん)「最初にお近くの警戒区域の情報を確認していただいて、大雨降った時などには市町村から出される情報を確認していただければと思います」
土砂災害警戒区域は県のホームページでも公開されています。