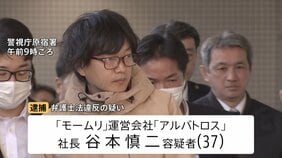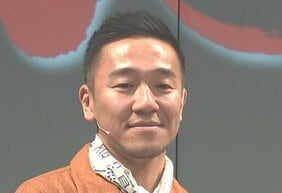検査で分かりにくい?
長期間咳が続き、マイコプラズマ肺炎が疑われる場合の検査としては、胸部レントゲン撮影やCTによる画像検査が行われる場合が有りますが、確定診断には鼻や喉から採取した粘液、痰を培養してマイコプラズマの有無を調べる方法があります。
しかし培養には特殊な培地が必要で、その培地も手に入りにくく、結果が分かるまでに2、3週間かかります。このため、実用的な検査とはいえません。血液検査で肺炎マイコプラズマに対する抗体を測定しますが、この検査も結果がでるのに時間がかかります。

近年、咽頭拭い液を用いた抗原迅速診断キットが広く用いられるようになっており、30分以内に結果がでる簡便な検査ですが、感度が高くないため、肺炎マイコプラズマ感染があったとしても陽性にならないことがあります。LAMP法やPCR法などの核酸増幅法は、精度が高い検査ですが、どの病院でも実施できるわけではなく、限られた施設でしか検査が出来ません。
‟隠れ患者”から感染拡大の可能性
【質問】
診断はつかないものの実際は感染している「隠れ患者」は多くいるとみられているのでしょうか?自覚がない方による感染の拡大も考えられるのでしょうか?
【回答】
マイコプラズマに感染しても多くの人は軽症で、1週間程度で治癒していくため普通の風邪との区別が難しいこともあります。症状が現れている時が最も感染を広げやすいと言われていますが、潜伏期間中や、症状が寛快した後も4~6週間程度は保菌状態に有ると言われています。このため、症状が軽い「隠れ患者」の人から感染が広がることも考えられます。