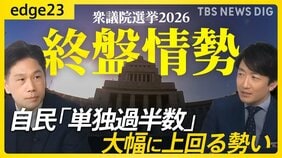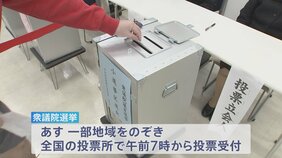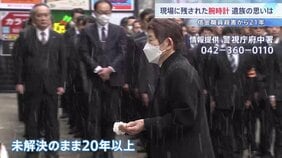線状降水帯の予測精度を向上するため、気象庁は、2025年の大雨のシーズンから海洋気象観測船を使った水蒸気観測を日本海でも実施すると明らかにしました。
能登地方では2024年9月、線状降水帯による記録的な大雨で16人が亡くなったほか、山形県でも7月に3人が死亡するなど、日本海側にも大きな被害をもたらしました。

線状降水帯の発生を予測するには、線状降水帯のもととなる水蒸気の量を把握する必要があり、気象庁の野村竜一長官は21日の定例記者会見で大雨のシーズン中、主に東シナ海に派遣している海洋気象観測船2隻のうち1隻を今年は日本海でも航行させる計画を明らかにしました。

気象庁・野村竜一長官「日本海でも線状降水帯ができやすい状況が進んでいたので、水蒸気の動きを日本海で見る必要があるということで船を回すことにした」
気象庁は2024年、線状降水帯の発生を事前に予測するいわゆる「半日前予測」を府県単位で発表する運用を始めましたが、予測を出して実際に線状降水帯が発生した「的中率」はおよそ10パーセントと、当初の想定を下回りました。
能登半島を襲った豪雨でも線状降水帯の発生を事前に予測することができず、気象庁は日本海側でも観測を強化することで予測精度の向上につなげたい考えです。