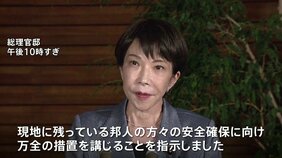高知市の中学校では、地域住民と生徒が協力し避難所を開設する訓練が行われました。訓練のリーダーを務めたのは、阪神・淡路大震災を経験した男性。男性が伝えたい思いとは。
(訓練放送)
「地震です、身を守ってください」
高知市の愛宕中学校では、阪神・淡路大震災があった1月17日に合わせて、避難訓練を行っています。学校は津波避難場所にも指定されていて、17日は近隣住民も訓練に参加しました。全員の避難が終わり、生徒会メンバーと住民が体育館に移動します。
(訓練リーダー・立道和男さん)
「建物は安全です。今から避難所を開設します」
体育館で行われるのは、避難所の開設訓練です。災害が起きた場合、愛宕中学校の体育館は避難所となり、地域住民と生徒たちが協力して運営していくことになります。
受け付けを設置する係。シートを敷き、通路と居住スペースを分ける係。簡易トイレをつくる係などそれぞれ役割が決められています。これら全ての係を取りまとめるのがリーダーの立道和男さんです。28年前の1月17日、立道さんは大阪で、阪神・淡路大震災を経験。その後の東日本大震災や熊本地震などでも被災地に赴き、避難所運営のノウハウを学んできました。今は高知で、知識や経験を若い世代に伝えています。
(立道和男さん)
「考えてどれが最善なのか、今何をしなくちゃいけないのか大事なのは誰かがやってくれるわけではない」
およそ30分で避難所の開設が完了。実際に受付をし、住民を受け入れる手順を確認していきます。最後に生徒自らが無線を使って、高知市の災害対策本部に避難状況を報告し、訓練は終了しました。リーダー立道さんは、一人ひとりが考えて動くことが大切だといいます。
(立道和男さん)
「誰かがやってくれるではなく自分に何ができるのかリアルタイムで考える。災害は何回も経験するものではない。経験がなくても自分たちを守ることができる知識と技術を身につけてほしい」
(生徒)
「今まで生徒だけでしかできなかったんですけど、協力してできることはこれかれもできればいいなと思いました」
「僕はこの地域に住んでいないので災害時どんな人が避難してくるのかわかったのでよかった」
災害時には手を取り合っていくことになる地域住民と生徒たち。これからも訓練を重ね、いざという時に備えます。