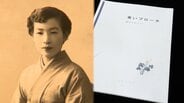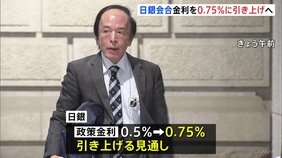~武田勝頼土佐の会ホームページによる、武田勝頼伝説~
武田勝頼土佐の会による、高知での武田勝頼伝説です。まず、勝頼は天目山で自害しておらず、影武者を使ったとされています。
その後は諸国をめぐり、武田家の末裔である香宗我部氏の住む土佐へ。そして土佐の戦国大名、長宗我部元親が高吾北地方を広く支配していた片岡氏を紹介し、高知県西部へと移り住んだということです。
仁淀川町大崎に住所を定めた勝頼は「大崎玄蕃」と変名。武田家の先祖を祀るための菩提寺、流光山成福寺や大崎八幡宮を建立するなどしたほか、九州で勃発した戸次川の戦いに参加しました。
このように、土佐の地でもさまざまな活躍を見せた勝頼ですが、1609年、64歳で亡くなり、鳴玉神社に葬られた、ということです。
一緒に葬られている三枝夫人は1616年に亡くなったとされているそうですが、歴史上に登場しない人物で、大きな謎だということです。
墓は今でもきれいな状態に⋯観光資源の一つとしても
いろいろな謎や不思議が残る高知の勝頼の墓ですが、今でも末裔が訪れて掃除をしているということで、記者が訪れた時もきれいな状態を保っていました。
故郷、山梨から離れた高知の地でも愛される甲斐の武将、勝頼。
仁淀川町では、今でも関連イベントが開催されているほか、県外からも墓を一目見ようという人が訪れるということで、町の観光資源の一つとなっているようです。