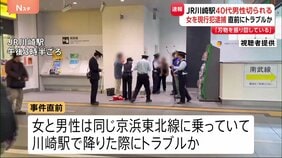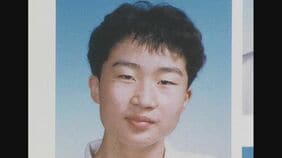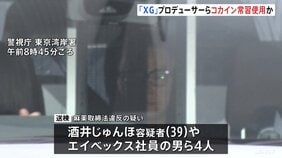自然豊かでのどかな高知県高知市春野町。山の中へ踏み入ると戦争の記憶が残されていました。身近な場所が戦場になったかもしれないということを今の私たちに伝える「戦争遺跡」を取材しました。
高知市春野町の森山地区。およそ800人が暮らしていて稲作やハウス栽培など、一次産業が盛んな地域です。

取材は7月。稲刈りを待つ稲穂に優しい雨が潤いを与え、しっとりとした光景が広がっていました。そんな森山地区、山に足を踏み入れてみると、尾根を囲むように掘られた、溝があります。

延長は400メートルほど。自然にできたとは考えにくいこちらの溝は、第二次世界大戦末期に日本軍が連合国軍の高知上陸に備えて作った「塹壕」です。塹壕とは敵の攻撃を防ぐために掘られた堀のこと。
高知市春野町の文化財について記された春野風土記によると春野町にはこうした塹壕を含む戦争遺跡が、およそ10か所確認されているといいます。

まだ見つかっていない物もあると考えられていて、のどかな田園地帯にも、かつて、戦争の足音が確実に歩み寄っていたことを痛切に感じます。
(戦争で父を亡くした中山寿賀子さん)
「写真でしか見たことないです。(Q.物心ついた時にはお父さんがいない)おらん。(Q.お父さんがいないのが当たり前)そうそう」

春野町に暮らす、中山寿賀子さん。父の亀幸さんが、終戦2か月前、ビルマ=現在のミャンマーで28歳という若さで病に倒れました。戦時中、春野地区からはおよそ1万人が動員され、そのうち800人の命が失われたと言われています。

「きこやん」の愛称で親しまれていた亀幸さんもその一人。1939年、高知市朝倉の陸軍部隊に入隊し、その後は南方の戦場に送られ、各地を転戦していました。

一度も、姿を見たことがない父。寿賀子さんの苦悩は戦争が終わった後も続き、父親がいないことでいじめられたこともあったといいます。苦悩したのは寿賀子さんだけではありません。
(戦争で父を亡くした中山寿賀子さん)
「お母さんが一番苦労されてます。お母さんも年寄り抱えて中々大変やったみたい。(戦争は)絶対にせられんということは分かるけど。私もいつも(戦争は)やめてほしいやめてほしいと思って、頭の中に残っちゅうき」

(畠中宏一さん)
「これがここから入りますよという(石碑)」
多くの悲しみを残した戦争の終結を象徴する碑が森山地区のとなり、西畑地区にあります。案内してくれたのは個人で春野町の戦争遺跡を調査している、佐川高校の畠中宏一(はたけなか・こういち)教諭です。

(畠中宏一さん)
「軍旗奉焼乃地です。軍旗を最後に焼いた場所になります」
高森山の奥深くにひっそりとたたずむ軍旗奉焼乃地の記念碑。陸軍の部隊が、終戦後の8月18日、部隊の旗である軍旗を焼いたことを記念した碑で戦没者の霊をまつる目的などで建てられました。

(畠中宏一さん)
「ここが44連隊(朝倉の部隊)が移ってきたところなのでこの山の周辺にはいろんな戦跡が残っている」
畠中さんは4年前まで、春野高校歴史同好会の顧問を務め、戦争遺跡を題材に生徒たちに郷土の歴史を教えていました。生徒を連れて、宿毛市や土佐清水市まで足を運んだこともあったといいます。
(畠中宏一さん)
「私でさえ戦争が終わってだいぶ経ってから生まれているような時代ですので、生徒にとって日本の戦争というのはものすごい遠い存在のように感じているわけです。けどひょっとしたらこの高知も戦場になったかもしれないということも知っていただいて、ガザ地区とかウクライナなどで戦争でいっぱい人が死んでいるということについても、自分が住んでいる場所から離れた場所の人のことも考えることができるような生徒になってもらいたいということから戦跡の見学もしました」
戦争遺跡から平和について学んでいた春野高校歴史同好会。しかし、2年前からはメンバーがいなくなり、現在は活動ができていません。
(畠中宏一さん)
「長い間、戦争を日本はしていないということで、そうなったときのことを想像するというのが中々難しいところはあると思います。ただこれから先、日本がどういう風になっていくか分からないので、戦争になった時に自分たちがどのようなことになるのか、ということも考える力は養っていく必要はあるんじゃないかなと思います」
終戦から79年。戦争の記憶をどう語り継いでいくかが課題となっています。「高知も戦場になったかもしれない」戦争遺跡がひっそりと伝え続けるその事実に目を向けることも、これからの世代に平和の尊さを伝える一つの方法です。