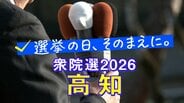地域の豊かな自然を生かした脱炭素社会の実現に取り組む梼原町。先日、町職員らが木質バイオマス発電の先進国ドイツを視察しました。からふるでは同行取材し、今週、特集でお伝えしています。最終日の15日は、「森林資源の価値」です。

南ドイツ最大の街、ミュンヘン。かつて、バイエルン王国の首都として栄えたこの街には、歴史あるドイツの街並みと近代的な建物が共存しています。ドイツ国内でも3番目に多い、150万人ほどが暮らす都市です。

1972年、この街でオリンピックが開催されました。当時建設されたオリンピアパークは、50年以上経過した今も人々を魅了し続けています。最大7万8000人が収容できるスタジアムは、いまでもサッカー大会などのスポーツイベントのほか、世界的なアーティストのコンサート会場としても使用されています。

ミュンヘンオリンピックは、歴史に暗い影を落とす事件が発生した大会としても知られています。選手村で、パレスチナの武装組織がイスラエルの選手とコーチ11人を人質に取り、殺害したのです。パーク内には犠牲者の追悼碑が設置され、悲劇を伝え続けています。

ミュンヘンから北西に80キロほど離れた町、アウクスブルク。レヒ川とヴェルタッハ川に挟まれた、水の豊かな町です。

レヒ川から水を引いた運河の入り口にはカヌーコースが整備されていて、ミュンヘンオリンピックの競技場にもなりました。

16世紀に「黄金のアウクスブルク」と呼ばれた街の中心部に建つのが、堂々たるたたずまいの市庁舎です。

1944年、第二次世界大戦による空襲で大規模な被害を受け修復された市庁舎。街の発展を誇らしげに示すのが、この”黄金の間”です。縦32.5m、横17.5m、高さが14mあり、部屋の壁や天井が黄金に輝いています。

正面や入り口にある木で作られた像も黄金!全部で2.6キロの金箔が使われていると言います。

天井の中心、およそ24平方メートルの絵に描かれた女性は、統治者には知恵が重要であることを表現しています。

(リポート:村山まや)
「アウグスブルクの街の中にはこうした美しい噴水があり、観光スポットにもなっています。まさに水の都です」

街の中には1300年代から築かれ始めたという水路が張り巡らされています。19世紀末になると、その水路に70もの水力発電所が誕生しました。運河の水でタービンを回し、発電した電気を路面電車に供給するなど、街の発展を支えてきました。

古くから自然の恵みを生かしてエネルギーを生み出してきたドイツ。地域での木質バイオマス発電によるエネルギー循環も進み、再生可能エネルギーの自給率はすでに半分ほどを占めています。

これに対し日本はまだ22%。今回の視察で梼原町の担当者は、脱炭素社会の実現に向け、改めて地域資源の重要性に気づかされたと話します。
(梼原町環境整備課 石川智也 副課長)
「一番感じたのは森林のエネルギーとしての価値をしっかりドイツの方は認識されている。梼原町もエネルギーとしての価値を高めていく必要があるのではないかと思う。そうすることで森林の循環、それに伴って経済の循環にもつながると感じた」

(梼原町環境整備課 中越光平さん)
「梼原の町のいいところもあるので、そういったところも踏まえつつ取り組んでいけたら」
2月6日、梼原町に新たな企業が誕生しました。その名も「ゆすはらエネルギー」です。町、森林組合、民間事業者が力を合わせ、町民と一緒になって脱炭素社会の実現を本気で目指します。
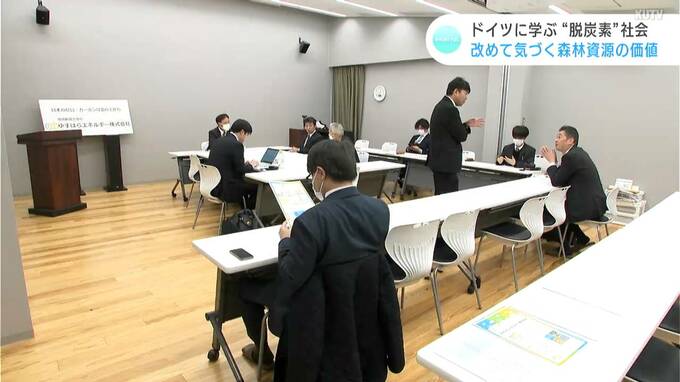
(吉田尚人 町長)
「しっかりとこの会社が未来に向かって健全経営ができ、そしてみなさんのお役に立っていけるように、お力をお貸しいただきたいと思います」
代表は西村新一(にしむら・しんいち)副町長。風力や水力、太陽光に加え、これからスタートする木質バイオマス発電を含む町内すべての再生可能エネルギーのマネジメントを行い、林業の活性化や地域の雇用創出にもつなげたい考えです。
(ゆすはらエネルギー代表 西村新一 副町長)
「エネルギーといえば電気ということもあるが人のエネルギー、町のエネルギーというところを考えれば元気、活力も含めて相対的に町が元気になるような会社にしていきたいと思っています」

1999年、四国カルストに建設した風車から始まった、梼原町の環境への取り組みは新たなステージを迎えました。
(リポート:村山まや)
「地球の未来のため世界中の国が目指す脱炭素化。日本から遠く離れたドイツと雲の上のまち梼原町は地域の資源を生かした脱炭素という同じ未来を目指しています」