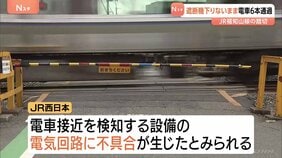《ヒグマの革製品を作る壁》

魅力のあるヒグマの革ですが、仕入れに壁があると、後藤さんは話します。
「革をなめして加工する大規模な工場が、北海道内にはないんです。エゾシカの革についても、本来は北海道の資源なのに、東京の会社を経由するので高くなってしまうし、仕入れたときにはどこで駆除された命なのかがわからない状態で来てしまう」
後藤さんは、エゾシカやヒグマの革を使った製品を作ることだけでなく、「トレーサビリティ」、その命の背景がわかる状態で製品を流通する仕組みを作ることを目標にしています。
どの地域で生きた、どんな個体だったのか。
性別や年齢まで、「命の背景を曖昧にせず、きちんと伝えることが、次の命を活かすことにつながる」と考えているといいます。

そのためには、北海道内のハンターから直接仕入れる体制が必要だといいます。どこで駆除された個体なのかをわかった上で、冷凍して個別に東京のなめし会社に郵送し、また同じ革を仕入れる仕組みです。
ただ、ハンターが駆除した直後に、きれいに解体して、皮が劣化しないように手間をかける必要があります。それだけのコストをかけて協力してくれるハンターを見つけることが大きな課題です。
ヒグマの革製品の価値が認められ、需要を高めることで、協力してくれるハンターにも収益を配分し、負担が少ない形を目指したいといいます。
簡単ではない道のりだからこそ、少しずつでも応援を必要としているのです。
「北海道の大事な資源が、ビジネスにだけされるのではなく、少しずつ仕組みを変えることで、命をつなぐ取り組みを広げていきたい」

駆除された命を、無駄にしないために。
そして、次の出没や被害を防ぐための、地域のクマ対策の資金に。
地域の一員として「自分だからできること」に挑戦する後藤さんの思いには、多くの反響があり、クラウドファンディングスタート初日から、第1段階の目標の200%を達成しました。
ただ、現在仕入れているクマの革は、応援購入した人への発送分でほとんど使い切る想定で、次の仕入れや製造のために、現在は100万円を目標にして、呼びかけを続けています。
文:幾島奈央
撮影:Haru(KEETS店内の写真)
※掲載の内容は取材時(2022年12月~2025年9月)の情報に基づきます。