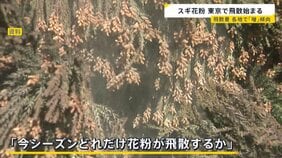◇《99年前の十勝岳噴火…あの悲劇を忘れてはいけない》
上富良野町に暮らす柴田真由美さん。祖父の大角伊佐雄さんが、99年前の大正泥流を目の当たりにした。
あの“悲劇”を消して忘れてはいけない…。祖父が絵に込めた思いをつなぐため、孫の柴田さんは、絵や額を修復。ここ数年、十勝岳が噴火した5月にあわせて、絵画展を開いている。
柴田真由美さん(52)
「いつ(十勝岳の)噴火が起こるかわからないということを、忘れずに言ってもらえるような取り組みを、今後続けていきたいと思っている」
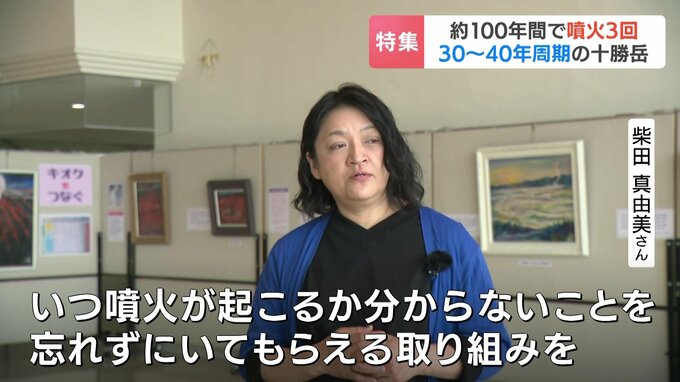
最後の噴火から37年ー。きょうも噴煙を上げながら、十勝岳は、雄大な姿を見せている。
森田絹子キャスター)
噴火災害は、様々ありますが、道の旭川建設部・事業室治水課の吉田栄治課長は『積雪期で、最も警戒しなければいけないのが“融雪型泥流”』と強調します。
気象台では、十勝岳をはじめ、北海道内にある、樽前山や北海道駒ヶ岳など、あわせて9か所を活火山として常時観測していますが、北海道は積雪期間が長いので、十勝岳に限らず特に警戒が必要です。

堀啓知キャスター)
ハード面の整備も進んでいるわけですが、99年前の映像が残っていることも驚きですし、被災地を辿るフットパスなど、過去の災害の記憶を具体的につなぐ活動も、災害への備えとして重要です。
大正泥流と噴火について描いた三浦綾子さんの小説『泥流地帯』を映画化する動きも、上富良野町を中心に進められているそうです。

過去の災害に学び、未来への教訓とする…私たちが取れる最大の備えではないでしょうか。