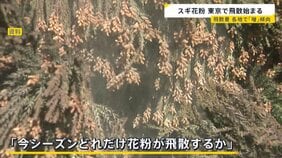◇《十勝岳の噴火は直近100年間に3回…泥流対策の巨大施設も》

大正泥流の36年後、1962年に再び噴火し、硫黄鉱山で働いていた5人が犠牲になっている。そして、その26年後の1988年にも、十勝岳は噴火。30年から40年周期で噴火を繰り返し、いまも大量の噴煙を上げている。

気象台は、十勝岳の火口を24時間監視している。現在、大規模な噴火につながる兆候は確認されていないが、熱活動は活発だという。
泥流被害の悲劇を繰り返さないため、巨大な施設が備えられている。全長917メートルにも及ぶ『2号透過型堰堤(えんてい)』である。

旭川建設管理部事業室治水課 吉田栄治課長
「ジャングルジムのような構造をしていて、巨石や流木を補足し、泥流の量を減らし、勢いを弱めることを目的にしている」
鋼材で作られたスリット構造の堰堤(えんてい)としては、世界最長の大きさだ。