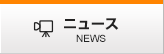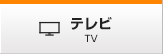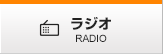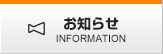お盆の盆提灯。
みなさんの家ではどんなタイプのものが飾ってあるでしょうか?
置くタイプに吊るすタイプ、そして様々な形…。
BSS取材班が、山陰の盆提灯事情を調査しました。
記者 三宅純人
「もうすぐお盆です。盆提灯と言えば、松江出身の私はこの置くタイプを想像するんですが、お店にはたくさんの種類の提灯があります。皆さんは盆提灯と言えばどれを想像しますか?」
島根県の松江、安来、鳥取県の米子に店舗を構える「仏壇のヤスヰ」で、山陰の盆提灯事情を聞きました。
仏壇のヤスヰ 安井達也社長
「こちらはですね、大内提灯といいます昔から伝統的にある提灯で日本全国あちこちで見られる提灯ですね」
3本の足で自立する大内提灯。一番オーソドックスなタイプです。

一方、こちらは吊るし提灯。つぼ型は岐阜提灯と呼ばれ、山陰全域でみられますが、長い筒状の形の住吉行燈は、特に米子・松江エリアでみられるそうです。


さらに・・・。
仏壇のヤスヰ 安井達也社長
「これは切子灯篭といいまして、特にこちらにあるのが安来が発祥の切子灯篭になります」
これは切子灯篭という提灯のうち、安来市発祥のもの。
手製の長い垂れ幕と切り絵細工が特徴で、非常に高価なものだといいます。

また、最近では、住宅事情などもあり、コンパクトで簡単に組み立てられるものも人気だとうことです。
様々なタイプがある盆提灯。
取材班が、山陰両県の仏具店に聞き取りした結果を総合すると、鳥取県全域、島根県西部は、置くタイプの大内提灯の家が多く、島根県東部は、置くタイプと吊るすタイプが半々くらいであることが分かりました。

しかし、タイプが違えど、ある共通点がみられるとのこと。
仏壇のヤスヰ 安井達也社長
「山陰地区はですね、全国に比べたら非常に皆さん高価な提灯を買われます。それはやはり山陰の方が、ご先祖様を供養するということに非常に熱心で思いが強いからじゃないかと思います」
あなたの家の盆提灯、どんなタイプでしょうか?