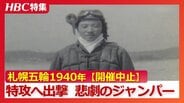■「 説1 戦国時代の防衛施設 」が決定的ではない理由:
街道の集落を守るための防衛施設とするならば、この石塁が当時使われていた古道、「中道往還」に接していない。近くには本栖の城山という山城がありますが、そこからも離れていて、連動性も感じられない。

更に、石の積み方が違います。中道往還に関連する石塁は、煉瓦積みのような非常に丁寧な積み方になっていますが、この石塁はとても簡単な積み上げ方ですので、防衛としての城山の石塁とは作った意図が違うのではないか。

■ 「説2 江戸時代の獣害を防ぐしし垣」が決定的ではない理由:
山梨県内でも「しし垣」の事例はありますが、これほど立派なものを造ったという記述がどの古文書に記されていません。江戸時代に造営されたのであれば、地域の伝承に残っているはず。
しかし、この石塁は1987年(昭和62年)に発見されるまで地元でも忘れ去られていたものなので、江戸時代よりも古い時代のものではないか。

■ 「説3溶岩流から守るための防護壁」が決定的ではない理由:
青木ヶ原溶岩流は5m~10mの厚さがあり、同じ程度の溶岩流を想定するのであれば、2m弱の壁では防ぎ切れないのではないか。

ということで、どの説も決め手に欠けるのです。