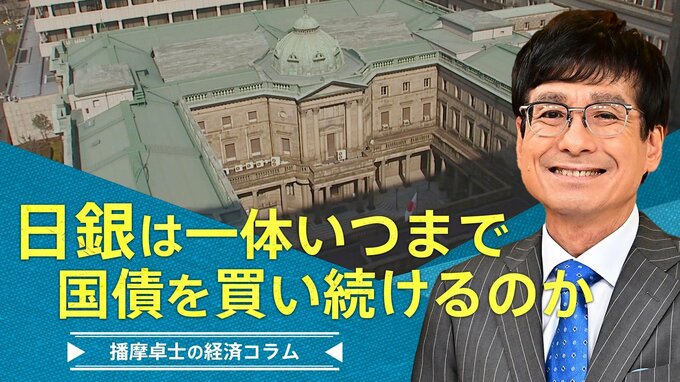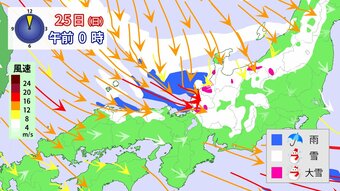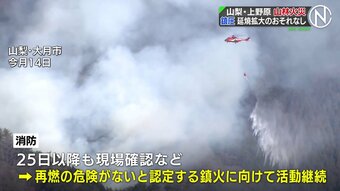日銀は7日、6月の長期国債の買い入れ額が16兆2038億円と、月間の買い入れ額として過去最高を更新したと発表しました。前の月の5月が7兆円余り、異次元緩和華やかなりし頃の、これまでの最高額が11兆円台ですから、16兆円がいかに大きな数字かわかります。これは、日銀がターゲットにしている長期金利(10年物国債の利回り)を0.25%以下に抑えるために、この水準で国債を無制限に買っているためです。
では0.25%に何か特別な意味があるのかといえば、そんなことはありません。日銀は現在、YCC=イールドカーブコントロールと言って、短期金利をマイナス0.1%に、長期金利を0%プラスマイナス0.25%の範囲に収めるという金融政策をとっており、0.25%というのは、0%の「のりしろ」、変動幅に過ぎません。この変動幅も当初はプラスマイナス0.1%で、その後、0.2%。0.25%と拡大して来た経緯があるほどです。
現在、日本で起きてる長期金利の上昇圧力は、世界中でインフレが進み、各国の中央銀行が金融引き締めに転じるなど、あらゆる国で長期金利が上昇している流れを受けたもので、その流れを止めることなどできません。ですから、いずれ日銀も長期金利の上昇を容認せざるを得ないと見る投資家は、金利の低い(つまり価格の高い)今のうちに日本国債を売っておこうと考え、それを日銀がどんどん買ってくれているという構図なのです。
日銀は、つい最近まで長年「長期金利は中央銀行がコントロールできない」ものだと言い、その理由として長期金利は、海外金利の動向やインフレ見通し、成長見通しなど多くの要素で決まるため、と説明していました。それが「0.25%死守」と、今やあまりの変わり様です。
短期間のオペレーションで長期金利の上昇圧力が収まればまだ良いでしょうが、そうでなければ日銀は国債を買い続けなければなりません。すでに日銀が保有する国債は、発行残高の5割を超えたと見られており、もはや日銀が財政をファイナンスしていると見られても仕方ない水準です。政治の世界では、「何でも赤字国債」「とりあえず赤字国債」とばかりに、財政規律は一層、緩んでいきます。また、日銀の長期金利抑え込みは、一層の円安を招き、輸入物価の高騰を加速させてしまうことにも批判が強まっています。
そして何より、いずれ日銀が長期金利の上昇を容認せざるを得なくなった時には、市場の振幅、つまり混乱をより大きくしてしまうことが問題です。現に3年物の国債を対象に同じようなYCCを導入していたオーストラリア中央銀行は、去年、市場の圧力に抗えず、突然、国債の無制限購入を停止、その際には金利が暴騰するという大混乱を招き、そのままYCC放棄に追い込まれるという悲惨な結末に終わっています。
海外金利の上昇が止まらない以上、この日銀の戦いに「勝ち目はない」と見る市場関係者が増えてきています。「勝てる手がない」と言っても良いかもしれません。だとすれば、勝ち目のない戦いを、さしたる合理性もない「自らの正当性」のために、いつまで続けるのでしょうか?
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)
注目の記事
引き取った子犬が翌日に急死「怒り心頭、助けてあげられずごめん」 ネット譲渡めぐりトラブル..."健康"のはずが重度の肺炎と診断 譲渡女性を直撃すると「病院ではなく自分で検査した」

「バイバイ」友達と別れた7秒後に最愛の娘(11)は命を奪われた 少女をはねた運転手の男(29)は「危険ドラッグ」を吸っていた 男の目は「焦点も定まらず反応もなかった」【女子児童 危険運転致死事件①】

横断歩道ではねられ首から下は麻痺…「あのとき死ねば」絶望の母を救った愛娘の言葉とは 車の運転やゴミ拾い… 車イスでも「できる」に変える母の挑戦

「海外旅行のように”宇宙”に行ける世界をつくりたい」28歳の若き経営者が目指す夢とは?地球と宇宙 "輸送" 技術の研究でつくる未来

交通事故死の8倍が“入浴中”に…富山が死亡率全国ワースト ヒートショック防ぐ「10分前暖房」「40℃」「半身浴」の鉄則

「雪で信号が見えない」長崎で目撃された現象 原因はLED化? ‟省エネ・高寿命‟が裏目に…盲点の雪トラブル