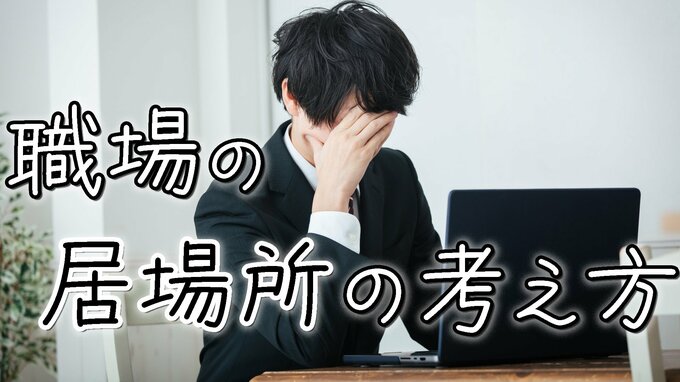転職して4カ月がたつ筆者。ここだけの話、新しい職場で少し居場所のなさを感じています。みんな温かく迎えてくれ、良くしてくれているのに、なぜでしょう。居場所について調べてみると、いわゆる人間関係の良さだけでは作れない「職場における居場所」の特性が見えてきました。
意外となかった働く人の「居場所」研究 児童期や青年期と異なる要素
ふとした瞬間に襲ってくる「自分、役にたっているのかな」という寂しく、むなしい感覚。昨秋に現在の会社に入った筆者は、時間が経てばなくなる感覚だろうと気にしないよう努めてきましたが、4カ月たってもなくなるどころか、増大しています。
今年こそは居場所がほしい…。これまで自分がいなくても回っていた職場で、新年からの存在感をどのように出すか悩み中の筆者に、居場所について教えてくれたのは、筑波大学の「働く人への心理支援開発研究センター」で研究員として働く中村准子さんです。
中村さん自身、インテリア関連から住宅関連の業界に転職した経験を持ちます。働きながら修士号を取り、最終的には生涯発達科学の博士号まで取得しています。
──どんな研究をしているか教えてください。
中村准子さん
「働く人の居場所の研究をしています。私が研究を始めたころは、居場所について、児童期や青年期の研究は多くありましたが、成人期以降の働く人を対象とした研究はなく、働く人にとっての居場所とは何だろうと、実際にインタビューやアンケート調査などをしました」
──働く人の居場所は、児童期や青年期の居場所と違うのでしょうか?
「大事だとよく言われる『人間関係が良い』だけでは居場所があるとは感じにくいということが調査結果から見えてきました。児童期や青年期の居場所には『人から受け入れられている』という要素がありますが、働く人の場合、この要素が独立しては出てこなかったんです。
たしかに、かつて働いていた時の自分自身を考えても、『受け入れられている』という感覚だけで居場所があるとはなかなか思えませんでした。働くということは、お金をもらって何かしら能力を提供して『役に立っている』という感覚を持つことができて初めて、『受け入れられている』という感覚が得られるのではないかなと思います」
──まさに、私も同じような感じです。職場はほとんどが良い人ですが、それでも居場所がないと感じています。働く人が居場所があると感じるために必要な要素は何なのでしょうか?
「調査結果からは、『他者から頼りにされ役に立っている』(=役割感)、『自分らしくいられる』(=本来感)、『安心して落ち着いていられる』(=安心感)の3つが働く人の居場所の要素としてあることが分かりました」
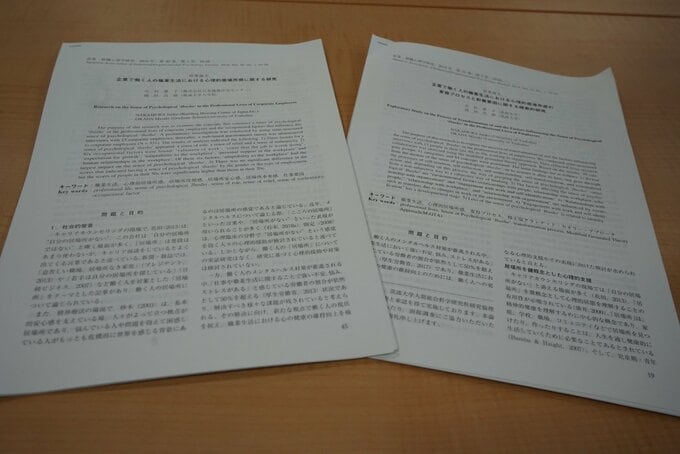
──たしかに、どれも自分は自信が持てないところです。
「仕事で評価されているのか、やりがいを感じられるのか、仕事そのものに愛着を持てているかという感覚がないと、居場所があるという感覚はなかなか得にくいのではないかと思います。
さらに、調査結果を分析してみると、働く人の居場所の『ある・なし』に影響を与えている要因の一つに『会社が私を成長させようと思ってくれているのか』という感覚があることが分かりました。成長させようという思いを感じれば『ここにいていいんだ』となるし、そういった思いが感じられないと『自分はいなくてもいい人間なのかな』となってしまいます」