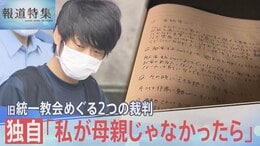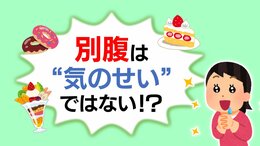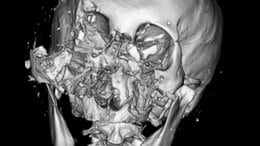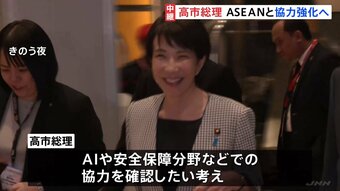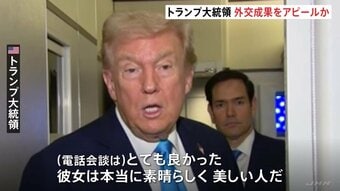米消費、景気は依然底堅く
14日に発表された11月の小売売上高は、そうしたシナリオに沿う内容でした。
前月比で0.3%の増加と市場予想の約0.1%減を上回り、2か月ぶりにプラス圏に戻りました。
10月は前月比マイナスで、「ついに過剰貯蓄も取り崩されたか」と、消費の先行きを懸念する向きもありましたが、年末商戦も堅調に推移しるようです。
今のところ、景気の腰折れを予感させる要素は顕在化していません。
その要因は様々でしょうが、ここに来てインフレ率が低下したため、アメリカでは実質賃金がプラスになっていることも大きいように思います。
FRBが重視するPCE(消費支出)物価指数は11月には2%台に低下するとみられる一方、平均時給は前年比4%の上昇が続いています。
実質賃金が19か月連続マイナスという日本とは景色が全く違うのです。
「3月利下げ開始」と市場は前のめり
その一方、金融市場の前のめりムードにもやや違和感があります。
FRBの姿勢転換を受けて市場では、来年・2024年3月に利下げに転換し、24年中に6回もの利下げを行うとの見通しが支配的になりつつあります。
利下げを期待する株式市場ではダウ平均が連日高値を更新する活況ぶりです。
しかし、6回も利下げするケースでは、景気が急減速している状態でしょうから、企業業績を考えても株価にはアゲインストな時でしょう。
現実には、2024年は景気の減速の度合いに目を凝らさなければならない年になりそうです。
政策には何よりタイミング
こうして見てくると、政策にはタイミングが一番重要だと、改めて思います。
当初、FRBは物価高を一時的と見誤り、引き締めに出遅れました。インフレ率を9.1%にまで高騰させたことは大失策だったと言えるでしょう。
しかし、その後は、「3回連続3倍速利上げ」など猛烈な引き締めに転じ、インフレの抑え込みにほぼ成功しました。
この間、副作用として表面化した地銀破綻も、大量の流動性供給で乗り切りました。
そして今、「利下げ視野」に転換したのも、なかなか見事です。
ひるがえって日本は、マイナス金利解除の時期を探り、長年の最大の課題である連続的な賃上げ実現に取り組むべき時を迎えています。
千載一遇のチャンスをものにできるのか、パーティー裏金問題で混乱する政治に足を引っ張られないように、タイミングを逃さないことが何より大事です。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)