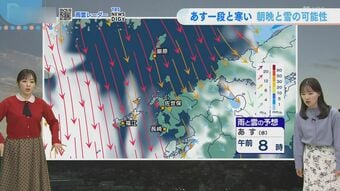ちょっとひととき…懐かしい “昭和の長崎”を感じてみてください。
NBCライブラリーに残る 昭和40年代の貴重な映像の一コマです。

「明治日本の産業革命遺産」として世界文化遺産に登録されている軍艦島(正式名称:端島)は かつて炭鉱の島でした。
日本の近代化に大きく貢献しましたが、主要エネルギーが石炭から石油へ移行する中で衰退の道を辿り、1974(昭和49)年1月に閉山しました。
その端島炭鉱のシンボルだった「立て坑やぐら」が取り壊されたのは、今からおよそ半世紀前のことでした。

やぐらの下には坑口があり、地下600メートルの垂直の立て坑が掘られていました。

やぐらには、地下約600メートルまで垂直に下降するエレベーターが取り付けられており、作業員たちは、やぐらの中を昇降するケージに乗って地下に降り、さらに奥の採炭現場に入っていったのです。

このやぐらは、遠くから見てもかなり目立ち、軍艦島のシンボル的存在でした。
1974(昭和49)年9月、閉山から8か月後のこの日、無人となった島でやぐらの解体作業が行なわれました。

戦艦土佐に似ているというところから「軍艦島」と呼ばれるようになった端島。
やぐらは高さ47メートル、まるで昔の軍艦の艦橋のような佇まいで、島全体を見下ろす形でそびえ立っています。
炭鉱マンを海底炭鉱へ送り込んだ立て坑 巻き揚げやぐらを解体する時が来ました。




鉄骨で組み上げたやぐらの足元を溶接機で切断、重機で慎重に引き倒し、ついにやぐらが横倒しになりました。


映像には感慨深げにこの作業を見守る作業員が映し出されています。
2009年に一般の方の上陸が解禁となり、現在では多くの観光客が訪れる人気観光スポットでとなった軍艦島。
現在、新型コロナが終息に向かうとともに多くのツアー客が戻って来ています。
放送局が撮影した 長崎の映像を配信している“ユウガク”より