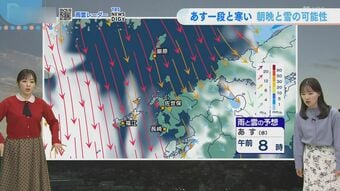一橋大学で経営管理を専門とする教授に話をお聞きしました。
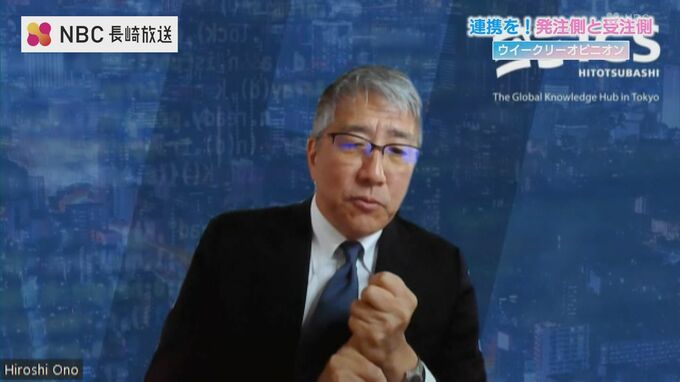
一橋大学 大学院 経営管理研究科 小野浩教授:
「昭和時代の働き方っていうのは “努力をして成果を出す”『成果が出ないんだったら、努力が足りないからだ』という風に決めつけちゃうわけですよね。
労働時間、働き方、物理的に出社している場合は、目の前に部下がいるから『こいつ一生懸命働いているな』っていうのが見える。一方で、“生産性”はあまり重視されなかった。“仕組みをいくら変えて” も “文化はついてこない”ところが、もたつかせている要因なのではないでしょうか」
【平】『働き方改革関連法』が施行されて4年半が経ちます。日本人の意識の部分や文化を変えるのには時間がかかるかもしれませんが、“労働時間”から“生産性”に尺度を変えていかなければ、経済成長で世界から置いていかれている日本はさらに置いていかれます。
【住】国際通貨基金(IMF)の最新の予測によると、今年の日本の名目GDPはドイツに抜かれ、4位に転落するという報道がありました。
“円安” 要因の一つには 日本の成長力の弱さ
【平】これは “ドルベース”だから『円安が問題なんだ』という指摘もありますが、そもそも、この “円安”は、日本の生産性の低さにも起因する『成長力の弱さ』を反映したものです。
円安は『海外と日本の金利差が要因だ』という論調がありますが、そもそも金利を上げるだけの “成長力”が日本にないことが根本的な原因です。
その克服するためにも、働き方改革を出発点として、生産性を向上させていかねばなりません。それが回り回って、長時間労働の改善、人手不足の解消、賃金の上昇につながっていくと思います。