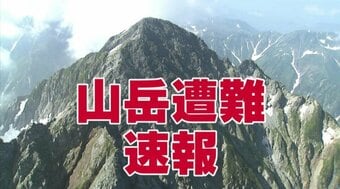季節外れの猛暑到来で東京電力管内には6月27日から4日連続で「電力需要ひっ迫注意報」が出されました。「無理のない範囲で節電をお願いします」という曖昧な表現に戸惑うと共に、その対象時間帯が「15時から18時」とか「15時から20時」とされたことに「えっ、どうして?」と感じました。夏の電力需要は、最も気温が上がる午後の14時頃が一番高くなると思っていたからです。
調べてみたところ、電力使用が最大になった時間帯は、私の直感通り、6月27日、29日が「13時から14時」、28日、30日が「14時から15時」でした。それは正しかったのです。しかし、使用実績(需要)を供給量で割った使用率でみると、この4日間共、最もひっ迫したのは午前中の「9時から10時」で、27、29、30日が使用率96%、28日が95%と、いずれも余力5%以下でした。結果的に、東京電力が節電を呼び掛けた夕方時間帯の使用率が午前より低かったのは、ピークを見越した揚水発電の稼働に加え、企業や家庭の節電努力が大きかったからです。これに対して電力使用が最大だった時間帯の使用率は、27日が92%、28、29,30日が90%に留まっていました。つまり、最大使用時には余力はそれなりにあったことになります。
なぜ電力の最大使用時に使用率がピークにならないのか?それは急速に広がった太陽光発電の供給量が時間と共に変化するからです。太陽光発電は、当然のことながら、日の出とともに発電が始まり、晴天であれば、太陽が最も高くなる正午前後に発電量がピークを迎え、午後は陽が西に傾くにつれて発電量は落ち、日没とともに再びゼロになります。つまり、太陽光発電の発電の供給量が大きいお昼前後は、需要の増大に対応できているのに対し、発電効率が落ちる朝方や夕方という時間帯に電力がひっ迫するというわけです。
実際、東京電力管内では、太陽光の発電量が最大になる正午前には、電力需要の25%以上を賄うに至っていますが、午前8時や夕方の16時には、太陽光の発電量は日中のピーク時の半分程度にまで落ちてしまいます。つまり、太陽光発電が普及すればするほど、供給量の変動=ボラティリティーが高まるというジレンマに直面しているのです。晴天の一日のうちだけでもこれだけの変動があるのですから、荒天時など日が全く射さない日があることを考えれば、その変動リスクがいかに大きいかわかります。同じ再生エネルギーでも今後の切り札とされる洋上風力発電では夕方以降、風が強まり発電量が増えるので、太陽光発電の減少を補えると期待されていますが、その実用化にはなお時間がかかりますし、こちらも、風が吹かなければ発電量が落ちることに変わりありません。
要は、時間帯や天候によって再生可能エネルギーの発電量が左右される以上、その落ち込みをカバーできるだけの、何らかの発電能力を持っていなければならないわけです。蓄電技術の向上はもちろん望まれるところですが、技術革新の難易度は高く、その間、火力発電への適切な新規投資の他、原子力発電の活用などが行われなければ、いつまでたっても電力不足から逃れられません。単に再生可能エネルギーを増やせば解決できるといった問題ではないのです。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)
注目の記事
【札幌タイヤ脱落事故】父親が語る加害者への憤り 52歳男は執行猶予中に無免許運転で逮捕 裏切られた裁判所の温情と、終わらない家族の苦しみ 当時4歳の娘は意識不明のまま

住宅街脅かす“不明管”…40年放置の責任はどこに? 「富山県は間に何もはいっていない」消えた公社が残した“負の遺産”に市も県も把握せず

東北730% 北海道420% 花粉が去年より大量? 飛散ピークに現れる“おぞましい虹”の正体

血液不足の危機 若者の「献血離れ」はなぜ起きたのか?30年で激減した『最初の一歩』と消えゆく学校献血

大好物は「紙」4年前に国内初確認の害虫「ニュウハクシミ」急拡大で博物館が大ピンチ、1点モノの文化財を守れ!学芸員が突き止めた弱点で撲滅へ

日本列島ほとんど“真っ赤”に… 週末15日から“10年に一度レベル”の「かなりの高温」に? 沖縄以外の北海道・東北・北陸・関東甲信・東海・近畿・四国・中国・九州・奄美で 気象庁が「早期天候情報」発表