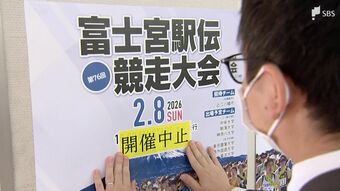取り消された再審開始決定 残る後悔

ー2014年、裁判長として再審開始と袴田さんの釈放を認めることに、ためらいはありましたか。
まず、前提として、裁判というのは独立していて、事件を担当している裁判官だけで結論を出します。周りから意見されるなどの影響を受けることは一切ありません。
ただ、当時調べた限りでは、裁判所の決定によって、死刑が確定した受刑者を釈放した前例はありませんでした。そもそも釈放ができるのか、いま、袴田さんを釈放までする必要があるのかという2点が問題になりますので、その点についても当然3人の裁判官で議論しました。
ー当時裁判官として、袴田事件から何を学びましたか。
あらためて、予断、偏見なく、事件に向き合うこと。そして、考え抜いた結果に従った結論を出すこと。裁判官としての勝負どころですね。
再審開始決定に至るまで、裁判官3人で充実した議論ができた。みな、それぞれ正面から正直に事件に向き合ったことは間違いない。非常に素晴らしい経験でした。本来あるべき裁判官としての合議を純粋にできたという意味で。
私自身は、袴田事件以外にも、心に残る事件があります。喜びと後悔、両方の思いがあります。あの事件と巡り合ったから自分は裁判官を続けることができた、裁判官をやっていてよかったという思い。一方で、あのときもっとできることはなかったのかという後悔もあります。袴田さんの場合は後者です。

再審開始決定を出してから再審公判開始までに9年もかかってしまった。決定文をどう書けば高裁で取り消されなかったのか。書き直せるならばどう書くか。いまだに考え続けています。
裁判官は当事者の言い分を聞く。その言い分が正しい場合も正しくない場合もありますが、民事であれば、なるべく紛争の適正な解決を目指す。刑事であれば、刑罰権の誤りなき実現を目指す。無罪の人を処罰してはいけないし、社会で更生する可能性を見極めていく必要がある。裁判官はそれぞれ性格やメンタリティは異なるにせよ、みな、同じように考えていると思います。
ー再審開始決定を不服として検察官が即時抗告(不服申し立て)したことに反論する意見書を、東京高裁に提出されましたね。
意見書については刑事訴訟法(第423条)に定められているので、それに従って書いたまでです。抗告が出てすぐに書いて送ったと思います。抗告申立書を読んだところ、再審請求審で議論したことを蒸し返しているような部分がほとんどだったので、そこにあまり時間をかけてほしくないという思いで書いたのですが、(高裁がその後再審開始を認めなかった)結果からみれば、あまり高裁には響いていなかったということですね。