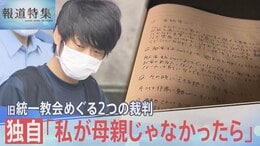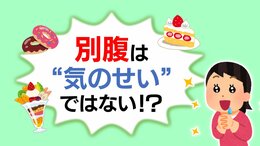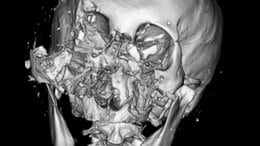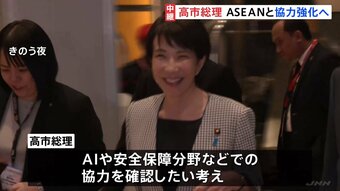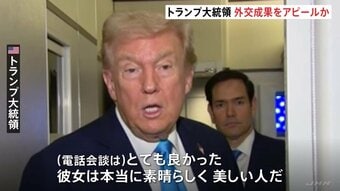GDPは「瞬間風速」だが、見える課題は深刻
前期比で見るGDPは、経済のいわば「瞬間風速」ですし、今後の統計発表を受けて修正されていくものです。先の述べたように今回は、在庫変動の寄与が大きかったので、速報値の数字そのものにあまり振り回される必要はありません。
しかし、▼需要項目がどれも悪かったこと、▼物価高が消費に深く、長く影響を与えていること、▼設備や住宅と言った投資にも物価高の現れていること、▼さらに人手不足などの供給力不足といった構造問題が投資の足を引っ張っていることなど、今回のGDPから見える課題はかなり深刻です。この数字を見る限り、「どこが好循環なんだ」と突っ込まれたら、答えようがないでしょう。
財政運営や金融政策にも影響か
「賃金が物価高に追いつかない」という実質賃金のマイナスは、9月で18か月連続です。経済対策での物価高対策の必要性は一層高まっています。「来年6月の減税実施」などと、悠長なことを言っている場合ではないような気がします。
内閣府の試算で4-6月期にようやくプラスに転じたマクロ的な需給ギャップも、恐らくマイナスに逆戻りすることでしょう。経済対策を素早く実行に移すことも求められそうです。
取り沙汰される日銀のマイナス金利解除のスケジュールにも微妙な影響を与えるかもしれません。「好循環」の実績が確認できない上に設備投資もマイナス続きなのに、「引き締めに転じることは妥当なのか」と、言われかねないからです。
7-9月期のGDP、実はこれだけ物価が上昇しながらも、名目GDPまでもが、前期比で僅かながらマイナスを記録しました。全く成長していない日本経済の姿を突き付けられた衝撃は、「好循環」への期待に、水を差すものになりました。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)